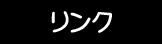●カメラ小僧の裏話5 僕がMになったワケ(全文無料公開)

下記の文章は、2011年12月31日、コミックマーケット81で発表した『カメラ小僧の裏話5 僕がMになったワケ』の全文です。(図解、挿絵除く)
図解、挿絵の入った完全版の冊子を希望される方は、ぜひ COMIC ZINによる委託販売 をご利用ください。
■はじめに
こんにちは、みちろうです。この度は『カメラ小僧の裏話5 僕がMになったワケ』をお手に取って下さり、誠にありがとうございます。
今回は「M属性を持つカメラ小僧がどのようにして生まれてくるのか」をテーマに筆を執りました。撮らせてくれる可愛い女の子の気を引きたくて、なんでもかんでも言うこと聞いちゃうカメラ小僧っているじゃないですか。何故そんな痛い人が大量に出てくるのか、その背景に迫りたいと思います。
今までの本では「よくあるエピソード」を交えて解説してきましたが、今回は無粋な解説をするよりも「M属性を持つカメラ小僧」の視点から「エピソード」をそのまま垂れ流しにした方が、直感的でわかりやすいのでは?と思い大幅に構成を変えてみました。ただのエッセイにも見えますが、評論のつもりです(汗。
冒頭から全編ぶっ通しで1つの物語となっています。あまり深く考えずに最初の少年時代の話から、主人公の心情や思考の流れをトレースしていってみて下さい。理解に苦しむ場面があってもそこはぬるくスルーで(汗。
毎回本を書く上で「今までの作品を超えるものを」との意気込みで取り組んでいます。今回はある意味それを大きく突き抜けました。そりゃあもうぶっちぎりで(汗。さすがに恥ずかしいので、さっさと売り捌いて音速で家に帰って引き篭りたいです。来年になったら何を書いたか忘れていることでしょう。きっと無かったことになっているので、たとえ筆者に会ってもこの本の内容には触れないで下さい(ぉ。
前置きが長くなりましたが、年始の初笑いにどうぞお役立て下さいませ。
2011年12月31日 コミックマーケット81にて
みちろう
今回は「M属性を持つカメラ小僧がどのようにして生まれてくるのか」をテーマに筆を執りました。撮らせてくれる可愛い女の子の気を引きたくて、なんでもかんでも言うこと聞いちゃうカメラ小僧っているじゃないですか。何故そんな痛い人が大量に出てくるのか、その背景に迫りたいと思います。
今までの本では「よくあるエピソード」を交えて解説してきましたが、今回は無粋な解説をするよりも「M属性を持つカメラ小僧」の視点から「エピソード」をそのまま垂れ流しにした方が、直感的でわかりやすいのでは?と思い大幅に構成を変えてみました。ただのエッセイにも見えますが、評論のつもりです(汗。
冒頭から全編ぶっ通しで1つの物語となっています。あまり深く考えずに最初の少年時代の話から、主人公の心情や思考の流れをトレースしていってみて下さい。理解に苦しむ場面があってもそこはぬるくスルーで(汗。
毎回本を書く上で「今までの作品を超えるものを」との意気込みで取り組んでいます。今回はある意味それを大きく突き抜けました。そりゃあもうぶっちぎりで(汗。さすがに恥ずかしいので、さっさと売り捌いて音速で家に帰って引き篭りたいです。来年になったら何を書いたか忘れていることでしょう。きっと無かったことになっているので、たとえ筆者に会ってもこの本の内容には触れないで下さい(ぉ。
前置きが長くなりましたが、年始の初笑いにどうぞお役立て下さいませ。
2011年12月31日 コミックマーケット81にて
みちろう
■目次
はじめに
目次
Chapter.1 カノジョなんてまだ早いと思ってた
Chapter.2 キミがいることで、自分の存在を感じられる
Chapter.3 僕は、いつだって、馬鹿で、身勝手だった
Chapter.4 そしてM属性だけが残った
おわりに
奥付
目次
Chapter.1 カノジョなんてまだ早いと思ってた
Chapter.2 キミがいることで、自分の存在を感じられる
Chapter.3 僕は、いつだって、馬鹿で、身勝手だった
Chapter.4 そしてM属性だけが残った
おわりに
奥付
■Chapter.1 カノジョなんてまだ早いと思ってた
カメラ小僧にも様々なタイプの人間がいる。紳士もいれば電波もいるし、尊大なやつもいれば卑屈なやつもいる。今回はその中でもコスプレイヤーやモデルの女の子に媚びへつらう下僕のようなカメラ小僧がテーマだ。とにかく女性のご機嫌を伺い、要望を聞き、弄ばれても耐え抜き「はい喜んで」「ですよねー」「我々の業界ではご褒美です」を連発するM男である。今までこの界隈を眺めてきた感覚としては、カメラ小僧全体の三割ほどがこのタイプに該当すると言えるだろう。
どのようしてそのようなタイプのカメラ小僧が出てくるのか、どうしてそのような思考になったのか、そのワケを辿ってみよう。その人間がどうしてMとなったのかを理解するためには、その人の半生を顧みる必要がある。特に少年時代からの恋愛事情は、その人間の人格形成に多大なる影響を及ぼすことはいうまでもないだろう。そこでまずは将来M属性のカメラ小僧となる人物の少年時代から実際にMになるまでを追っていくこととする。少し長丁場のストーリーとなるがどうかお付き合い頂きたい。
なお、以下は取材と調査に基づき、脚色を織り交ぜた『よくあるエピソード』である。内容がフィクションかノンフィクションかの判断は読者のご想像にお任せしたい。
どのようしてそのようなタイプのカメラ小僧が出てくるのか、どうしてそのような思考になったのか、そのワケを辿ってみよう。その人間がどうしてMとなったのかを理解するためには、その人の半生を顧みる必要がある。特に少年時代からの恋愛事情は、その人間の人格形成に多大なる影響を及ぼすことはいうまでもないだろう。そこでまずは将来M属性のカメラ小僧となる人物の少年時代から実際にMになるまでを追っていくこととする。少し長丁場のストーリーとなるがどうかお付き合い頂きたい。
なお、以下は取材と調査に基づき、脚色を織り交ぜた『よくあるエピソード』である。内容がフィクションかノンフィクションかの判断は読者のご想像にお任せしたい。
□少年が夢見た恋愛観
小さい頃から僕は「悪者によって高い塔に閉じ込められたお姫様を、男の子が助け出す物語」が大好きだった。
『ルパン三世 カリオストロの城』や『天空の城ラピュタ』などの映画ではクラリスやシータの救出劇にワクワクしたし、『ゼルダの伝説神々のトライフォース』や『ロビンフッドの大冒険』ではお城に幽閉されていた姫君を一度助け出した上で、教会やシャーウッドの森に匿いながら悪漢と対峙する展開に胸を躍らせた。
ときには主人公が力及ばず、もう少しでヒロインを救い出せるというところで警備兵に捕えられてしまう作品もあった。二人が再び引き離されながらも「必ずっ、必ず迎えに来るからっ!」と主人公がもがき叫び、ヒロインがその言葉を信頼して救い出してくれるのを再び待つというシチュエーションにもとても興奮した。運命が二人の逢瀬を邪魔するのである。君も男なら聞き分けたまえ。
ヒロインを救い出そうとする勇敢な主人公に憧れ、僕もそんな風になりたいと思っていた。子供心に「女の子を悪いやつから守るような、つよくやさしい男の子になりたい」というナイト願望があったのである。
積極的に救出しようとする冒険活劇とは別に、もう一つ憧れたものがある。偶発的なトラブルによって男の子と女の子が出会い、状況的に急接近する羽目になるというボーイミーツガールの物語だ。
日常を過ごす主人公のところにトラブルを抱えた女の子が現れ「助けて!悪漢に追われてるの」あるいは「記憶を無くして、これからどうすればいいかわからないの」と転がり込んでくるパターンである。こっそり女の子を自分の家に匿い、奇妙な同居生活(同棲ではない)をしていくにつれて、主人公の日常に少しづつ変化が訪れるというシチュエーションだ。
こちらの場合、主人公は「自宅に女の子がいる」という状況に困りながら(とはいえ内心嬉しくない筈がない)も基本的に日常を送り続ける。そして徐々に安心を取り戻した彼女に、主人公の日常をかき混ぜられてしまうお約束の展開だ。
まぁエロゲによくあるパターンだが、どちらかというと小学生の頃は「家族以外の女の子がそばにいることで、何か自分自身が大きく成長出来そうなモノ」がありそうな気がした。このつまらない毎日をかき混ぜて波乱に満ちたものにしてくれることを心のどこかで期待したのだ。
マンガやアニメの世界とは裏腹に、現実の小学生時代の僕がどうだったかというと、とてもじゃないが「つよくやさしい男の子」からはほど遠い少年だった。思春期を迎える前であり、性を意識してエッチな妄想モードに入るようなことは無かったが、単に「女の子を守る、助ける存在になる」ということが恥ずかしかったのである。
当時可愛いな、と思っていた女の子からラブレターを貰ったことを今でも覚えている。放課後に教室を出るとき彼女から急にチューされたことも覚えている。が、僕は全力で拒絶した。酷い言葉で罵り、顔に唾を吐き、その場から逃げ出した。彼女は泣き崩れ、後で先生には怒られ、クラス全員の前で謝罪させられた。
どう考えても100%僕に非があるし、今更弁解もクソもないのだが、やはり当時は幼過ぎたのだ。女の子と仲良くなんかしてたら、友達からからかわれて仲間外れにされてしまうとでも考えたのだろう。
またあるときは、女の子が「ゲーム機たくさん持ってたよね?君の家に遊びに行っていい?」と言いながら拒否するヒマもなく押しかけてきたこともある。「自宅に女の子がいる」という状況に困りながら(とはいえ内心嬉しくない筈がない)あれこれ得意げにゲームをプレイして見せた。難しいステージを進む様子を「すごいすごい」と囃す彼女に僕は鼻高々になりながら、でもそれ以降二度と彼女を自宅に寄らせることはなかった。なんのことはない。『ドラゴンクエスト3』で勇者の名前を自分に、女僧侶の名前を彼女にして冒険していた。そのセーブデータだけは絶対に他人に見られる訳にはいかなかったのである。
今振り返ってみれば、あれはいわゆる「いい雰囲気」だったのだと思う。それに女の子が頻繁に家に遊びに来るようなシチュエーションは、当時の僕自身が望んでいたことだったはずだ。だが、そういう状態になることで日常の「ナニか」が変化することを恐怖した僕は、フラグをバッキバキの完膚無きまでにへし折っていた。
恋愛かどうかはともかく、女の子との関係性の理想像を思い描きながら、一方で現実にそのような関係になることが照れ臭くて、行動に移すことはおろか、男友達だけで楽しく遊ぶ毎日が続くことを望んでしまったのである。
『ルパン三世 カリオストロの城』や『天空の城ラピュタ』などの映画ではクラリスやシータの救出劇にワクワクしたし、『ゼルダの伝説神々のトライフォース』や『ロビンフッドの大冒険』ではお城に幽閉されていた姫君を一度助け出した上で、教会やシャーウッドの森に匿いながら悪漢と対峙する展開に胸を躍らせた。
ときには主人公が力及ばず、もう少しでヒロインを救い出せるというところで警備兵に捕えられてしまう作品もあった。二人が再び引き離されながらも「必ずっ、必ず迎えに来るからっ!」と主人公がもがき叫び、ヒロインがその言葉を信頼して救い出してくれるのを再び待つというシチュエーションにもとても興奮した。運命が二人の逢瀬を邪魔するのである。君も男なら聞き分けたまえ。
ヒロインを救い出そうとする勇敢な主人公に憧れ、僕もそんな風になりたいと思っていた。子供心に「女の子を悪いやつから守るような、つよくやさしい男の子になりたい」というナイト願望があったのである。
積極的に救出しようとする冒険活劇とは別に、もう一つ憧れたものがある。偶発的なトラブルによって男の子と女の子が出会い、状況的に急接近する羽目になるというボーイミーツガールの物語だ。
日常を過ごす主人公のところにトラブルを抱えた女の子が現れ「助けて!悪漢に追われてるの」あるいは「記憶を無くして、これからどうすればいいかわからないの」と転がり込んでくるパターンである。こっそり女の子を自分の家に匿い、奇妙な同居生活(同棲ではない)をしていくにつれて、主人公の日常に少しづつ変化が訪れるというシチュエーションだ。
こちらの場合、主人公は「自宅に女の子がいる」という状況に困りながら(とはいえ内心嬉しくない筈がない)も基本的に日常を送り続ける。そして徐々に安心を取り戻した彼女に、主人公の日常をかき混ぜられてしまうお約束の展開だ。
まぁエロゲによくあるパターンだが、どちらかというと小学生の頃は「家族以外の女の子がそばにいることで、何か自分自身が大きく成長出来そうなモノ」がありそうな気がした。このつまらない毎日をかき混ぜて波乱に満ちたものにしてくれることを心のどこかで期待したのだ。
マンガやアニメの世界とは裏腹に、現実の小学生時代の僕がどうだったかというと、とてもじゃないが「つよくやさしい男の子」からはほど遠い少年だった。思春期を迎える前であり、性を意識してエッチな妄想モードに入るようなことは無かったが、単に「女の子を守る、助ける存在になる」ということが恥ずかしかったのである。
当時可愛いな、と思っていた女の子からラブレターを貰ったことを今でも覚えている。放課後に教室を出るとき彼女から急にチューされたことも覚えている。が、僕は全力で拒絶した。酷い言葉で罵り、顔に唾を吐き、その場から逃げ出した。彼女は泣き崩れ、後で先生には怒られ、クラス全員の前で謝罪させられた。
どう考えても100%僕に非があるし、今更弁解もクソもないのだが、やはり当時は幼過ぎたのだ。女の子と仲良くなんかしてたら、友達からからかわれて仲間外れにされてしまうとでも考えたのだろう。
またあるときは、女の子が「ゲーム機たくさん持ってたよね?君の家に遊びに行っていい?」と言いながら拒否するヒマもなく押しかけてきたこともある。「自宅に女の子がいる」という状況に困りながら(とはいえ内心嬉しくない筈がない)あれこれ得意げにゲームをプレイして見せた。難しいステージを進む様子を「すごいすごい」と囃す彼女に僕は鼻高々になりながら、でもそれ以降二度と彼女を自宅に寄らせることはなかった。なんのことはない。『ドラゴンクエスト3』で勇者の名前を自分に、女僧侶の名前を彼女にして冒険していた。そのセーブデータだけは絶対に他人に見られる訳にはいかなかったのである。
今振り返ってみれば、あれはいわゆる「いい雰囲気」だったのだと思う。それに女の子が頻繁に家に遊びに来るようなシチュエーションは、当時の僕自身が望んでいたことだったはずだ。だが、そういう状態になることで日常の「ナニか」が変化することを恐怖した僕は、フラグをバッキバキの完膚無きまでにへし折っていた。
恋愛かどうかはともかく、女の子との関係性の理想像を思い描きながら、一方で現実にそのような関係になることが照れ臭くて、行動に移すことはおろか、男友達だけで楽しく遊ぶ毎日が続くことを望んでしまったのである。
□初恋は隣の席の女の子
無邪気でいられた小学生の頃とは異なり、思春期を迎えると嫌が追うにも異性を意識せざるを得なくなる。小学校の卒業式の日に初めて見る、女子のクラスメイトの制服姿によって男としての「ナニか」が目覚めてしまうのだ。昨日までデニムのオーバーオールで少年みたいだった女の子が、プリーツスカートをなびかせているのを見てしまうと、もはや無垢ではいられなくなる。女の子が心なしか急に可愛くエロく見えてきて緊張してしまうのである。
僕は生まれて初めて感じるエッチな感情に、どう対していいかわからなくなった。夏はブラウスからうっすらとブラが透けて見えるし、冬は冬で黒いストッキングのグラデーションから視線を外せなくなってしまう。中学はまだ男女とも同じ教室で着替えるため、体育の時間などは悶々しまくって仕方がなかった。誰だって校舎の階段やベランダ付近で何でもないフリをして上を見上げ、手すりにもたれ掛かる女子のスカートの中の白い逆三角形を目に焼き付けたはずだ。
女子のことが気になって気になって仕方がないくせに、一方でどう接していいのかわからなくなった。積極的に交流するのがどうしても恥ずかしくて、勇気が出せなくて、僕は男友達だけで遊ぶようになってしまったのだ。
ただ完全にコミュニケーションを断ってしまった訳ではなく、女の子から話し掛けられるのをずーっと待っていた記憶はある。というか、話し掛けてもらうためのきっかけ作りに涙ぐましい努力をしていた。消しゴムが落ちたら拾ってあげてお礼を言ってもらうとか、教室で僕にも分かる話題で盛り上がってるときにはさり気なくその場の隅にいて話を振ってもらうのを待っているとか、今考えれば「情けなさ過ぎる全然ダメじゃん」という行動ばかりだが、当時はそれでちょっとでも女の子との会話が成立すれば、その日一日ハッピーだったのである。
今思えば初恋も中学2年の頃だった。初恋の相手はポニーテールの女の子で、彼女は誰にでも分け隔てなく話し掛けてくれる女の子だった。女子からすると僕はクラスの中でもひどく目立たない存在だったはずだが、彼女はそんな僕にも積極的に話し掛けてくれたのだ。僕の良いところを見つけて褒めてくれたり、屈託なく自分のことを話してくれたりした彼女のことを、いつしか意識するようになっていた。未だ何かを聞かれたら答えるだけで、僕から話しけるようなことはほとんどなかったが、彼女と会話になれば調子に乗って多少なりとも饒舌になったり、一生懸命面白いことを言おうとした。
そんな淡い恋路に奇跡が起こる。神の悪戯か、席替えのくじ引きで彼女と隣同士になったのである。好きな女の子が隣にやってきて「やっほー」と手を振ってきたときには一瞬何が起こったのかわからなかった。「俺も席替えを楽しみたい」と黒板の席次表にくじ番号をランダムに書き入れていった担任の先生、あなたが神か。
天にも昇る気持ちだった反面、彼女を目の前にして好きだと言えずにいた僕は、そんな感情をおくびにも出さずただ「よろしく」とだけ返した。すると彼女は笑顔を見せながら「よろしくねー」といいつつ握手を求めてくるではないか。正直握手したとき少し顔がニヤ付いていたかもしれない。彼女が隣に座ることが決定した瞬間、僕はもう一生席替えをしたくないと思ったものだ。
それから毎日が楽しくて楽しくて仕方がなかった。「今日の髪形どうかな?かわいい?」とか「これでも部活で多少は筋肉付いたんだよ?ふくらはぎ触ってみて」などリアルラブプラス状態だったのである。彼女は少し病弱でときどき学校を休むこともあったが、こっちはこっちで彼女と隣同士になれる時間を絶対に減らすまいとたとえ熱があっても学校に行った。お陰で中学は皆勤賞である。
さて、一見リア充な青春時代にも見える訳だが、基本的に彼女側から話し掛けてきてくれたからこそ成立していたつかの間の夢である。修学旅行のとき、こっそり深夜に女の子たち(彼女含まず)が僕たちの部屋に遊びに来て、ヒソヒソ話で女子側の本音トークを教えてくれた。まぁよくある「○○ちゃんは△△くんのこと好きらしいよ?」的なゴシップネタである。あろうことか、そのときに彼女の恋愛事情を全部聞いてしまったのである。結論から言えば、とっくの昔から彼氏がいたそうだ。
そもそも「中学の修学旅行で深夜2時に隣の布団で女の子が寝てるってそれなんてエロゲ?」状態なのだが、僕はそれどころではなかった。彼女の彼氏の存在を知ろうが知るまいが、最初から告白する勇気はなかったし、どのみち最後まで何のアプローチもしなかっただろうが、やはり初めての失恋はショックだったのである。泣きたかった。死にたかった。
それから毎日が天国で地獄だった。好きな女の子と席が隣同士なのだ。僕の内向的なところを気にせず毎日楽しく話し掛けてくれた。ときどきツッコミを入れてくれた。毎日傍で彼女の笑顔を見ていることが出来たのだ。これほど幸せなことはなかった。
一方で彼女はすでに付き合ってる相手がいた。僕はそれを知らないことになっていた。いやそれ以前に僕が彼女に恋をしていることは誰も知らなかった。だから落ち込む顔も出来なかったのだ。これほど辛いこともないと思った。
修学旅行以降も周囲の日常は何も変わらなかったが、僕だけが正常ではいられなかった。嬉しいと悔しいの感情が同時に溢れてきて、頭がどうにかなりそうだったのだ。どうすることも出来なかった。勝手に彼女を好きになって、勝手に彼女の秘密を知って、勝手に彼女を諦めたのだ。誰も悪くない。でも辛くて、悔しくて、苦しい。
だがそれでも、彼女のことが好きで好きで仕方ないことには変わりがなかった。今さら嫌いになんかなれなかった。彼女にどうしても会いたくて、毎日欠かさず学校に行ってしまう。そして、彼女の笑顔を引き出したくてクラスのいじられ役を率先して演じてしまっていた。彼女は僕の隣の席で笑っていた。なんだかんだ言ってその時間は温かかった。たとえ既に彼氏がいたとしても、その時間は幸せだったのである。
高校受験の段階になり、少し背伸びして県内屈指の進学校を受けた。成績はボーダーラインぎりぎりだ。落ちれば即高校浪人決定の背水の陣である。
受験前日の学校から帰るとき、校門に彼女がいた。自分のことを待っていてくれてる…なんてことは100%有り得ないので「期待しない期待しない…」と心に念じて軽くバイバイと手を振ると「頑張ってね。君は頭がいいからきっと大丈夫だよ」と言って近くに来て肩をパンパン叩いてくれたのを覚えている。なんというか、泣きそうになってしまった。
彼女は別の高校を受験する。中学を卒業したらもう会えなくなる。せめて僕の気持ちを知ってもらいたい…。苦しみから解放されてラクになりたい…。だが関係が終わる最悪のタイミングで告白なんて出来る勇気があるはずもなく、結局最後の最後まで何も伝えることは出来なかった。
結局のところ当時「彼氏になれなくてもいい。毎日傍で笑顔さえ見ていられれば」と考えていた時点で既に自分自身に負けていたといえる。「好きだから何が何でも付き合いたい」と玉砕覚悟でアタックしていたなら(いや状況からして玉砕は決定的なのだが)、もしかしたらその後の人生は変わっていたかもしれない。
僕は生まれて初めて感じるエッチな感情に、どう対していいかわからなくなった。夏はブラウスからうっすらとブラが透けて見えるし、冬は冬で黒いストッキングのグラデーションから視線を外せなくなってしまう。中学はまだ男女とも同じ教室で着替えるため、体育の時間などは悶々しまくって仕方がなかった。誰だって校舎の階段やベランダ付近で何でもないフリをして上を見上げ、手すりにもたれ掛かる女子のスカートの中の白い逆三角形を目に焼き付けたはずだ。
女子のことが気になって気になって仕方がないくせに、一方でどう接していいのかわからなくなった。積極的に交流するのがどうしても恥ずかしくて、勇気が出せなくて、僕は男友達だけで遊ぶようになってしまったのだ。
ただ完全にコミュニケーションを断ってしまった訳ではなく、女の子から話し掛けられるのをずーっと待っていた記憶はある。というか、話し掛けてもらうためのきっかけ作りに涙ぐましい努力をしていた。消しゴムが落ちたら拾ってあげてお礼を言ってもらうとか、教室で僕にも分かる話題で盛り上がってるときにはさり気なくその場の隅にいて話を振ってもらうのを待っているとか、今考えれば「情けなさ過ぎる全然ダメじゃん」という行動ばかりだが、当時はそれでちょっとでも女の子との会話が成立すれば、その日一日ハッピーだったのである。
今思えば初恋も中学2年の頃だった。初恋の相手はポニーテールの女の子で、彼女は誰にでも分け隔てなく話し掛けてくれる女の子だった。女子からすると僕はクラスの中でもひどく目立たない存在だったはずだが、彼女はそんな僕にも積極的に話し掛けてくれたのだ。僕の良いところを見つけて褒めてくれたり、屈託なく自分のことを話してくれたりした彼女のことを、いつしか意識するようになっていた。未だ何かを聞かれたら答えるだけで、僕から話しけるようなことはほとんどなかったが、彼女と会話になれば調子に乗って多少なりとも饒舌になったり、一生懸命面白いことを言おうとした。
そんな淡い恋路に奇跡が起こる。神の悪戯か、席替えのくじ引きで彼女と隣同士になったのである。好きな女の子が隣にやってきて「やっほー」と手を振ってきたときには一瞬何が起こったのかわからなかった。「俺も席替えを楽しみたい」と黒板の席次表にくじ番号をランダムに書き入れていった担任の先生、あなたが神か。
天にも昇る気持ちだった反面、彼女を目の前にして好きだと言えずにいた僕は、そんな感情をおくびにも出さずただ「よろしく」とだけ返した。すると彼女は笑顔を見せながら「よろしくねー」といいつつ握手を求めてくるではないか。正直握手したとき少し顔がニヤ付いていたかもしれない。彼女が隣に座ることが決定した瞬間、僕はもう一生席替えをしたくないと思ったものだ。
それから毎日が楽しくて楽しくて仕方がなかった。「今日の髪形どうかな?かわいい?」とか「これでも部活で多少は筋肉付いたんだよ?ふくらはぎ触ってみて」などリアルラブプラス状態だったのである。彼女は少し病弱でときどき学校を休むこともあったが、こっちはこっちで彼女と隣同士になれる時間を絶対に減らすまいとたとえ熱があっても学校に行った。お陰で中学は皆勤賞である。
さて、一見リア充な青春時代にも見える訳だが、基本的に彼女側から話し掛けてきてくれたからこそ成立していたつかの間の夢である。修学旅行のとき、こっそり深夜に女の子たち(彼女含まず)が僕たちの部屋に遊びに来て、ヒソヒソ話で女子側の本音トークを教えてくれた。まぁよくある「○○ちゃんは△△くんのこと好きらしいよ?」的なゴシップネタである。あろうことか、そのときに彼女の恋愛事情を全部聞いてしまったのである。結論から言えば、とっくの昔から彼氏がいたそうだ。
そもそも「中学の修学旅行で深夜2時に隣の布団で女の子が寝てるってそれなんてエロゲ?」状態なのだが、僕はそれどころではなかった。彼女の彼氏の存在を知ろうが知るまいが、最初から告白する勇気はなかったし、どのみち最後まで何のアプローチもしなかっただろうが、やはり初めての失恋はショックだったのである。泣きたかった。死にたかった。
それから毎日が天国で地獄だった。好きな女の子と席が隣同士なのだ。僕の内向的なところを気にせず毎日楽しく話し掛けてくれた。ときどきツッコミを入れてくれた。毎日傍で彼女の笑顔を見ていることが出来たのだ。これほど幸せなことはなかった。
一方で彼女はすでに付き合ってる相手がいた。僕はそれを知らないことになっていた。いやそれ以前に僕が彼女に恋をしていることは誰も知らなかった。だから落ち込む顔も出来なかったのだ。これほど辛いこともないと思った。
修学旅行以降も周囲の日常は何も変わらなかったが、僕だけが正常ではいられなかった。嬉しいと悔しいの感情が同時に溢れてきて、頭がどうにかなりそうだったのだ。どうすることも出来なかった。勝手に彼女を好きになって、勝手に彼女の秘密を知って、勝手に彼女を諦めたのだ。誰も悪くない。でも辛くて、悔しくて、苦しい。
だがそれでも、彼女のことが好きで好きで仕方ないことには変わりがなかった。今さら嫌いになんかなれなかった。彼女にどうしても会いたくて、毎日欠かさず学校に行ってしまう。そして、彼女の笑顔を引き出したくてクラスのいじられ役を率先して演じてしまっていた。彼女は僕の隣の席で笑っていた。なんだかんだ言ってその時間は温かかった。たとえ既に彼氏がいたとしても、その時間は幸せだったのである。
高校受験の段階になり、少し背伸びして県内屈指の進学校を受けた。成績はボーダーラインぎりぎりだ。落ちれば即高校浪人決定の背水の陣である。
受験前日の学校から帰るとき、校門に彼女がいた。自分のことを待っていてくれてる…なんてことは100%有り得ないので「期待しない期待しない…」と心に念じて軽くバイバイと手を振ると「頑張ってね。君は頭がいいからきっと大丈夫だよ」と言って近くに来て肩をパンパン叩いてくれたのを覚えている。なんというか、泣きそうになってしまった。
彼女は別の高校を受験する。中学を卒業したらもう会えなくなる。せめて僕の気持ちを知ってもらいたい…。苦しみから解放されてラクになりたい…。だが関係が終わる最悪のタイミングで告白なんて出来る勇気があるはずもなく、結局最後の最後まで何も伝えることは出来なかった。
結局のところ当時「彼氏になれなくてもいい。毎日傍で笑顔さえ見ていられれば」と考えていた時点で既に自分自身に負けていたといえる。「好きだから何が何でも付き合いたい」と玉砕覚悟でアタックしていたなら(いや状況からして玉砕は決定的なのだが)、もしかしたらその後の人生は変わっていたかもしれない。
□二次元の魔法に魅了された高校時代
「お前、もしかして魔法とか使えるんじゃね?」とか真顔で馬鹿にされ始めたのは高校に入ってからだ。三十路まで童貞だと魔法使いになれる──というスラングが出てきたのは2ch文化が出てきてからだったが、僕は15歳で既に魔法使い扱いだった。
教室の中で浮いている自覚はあったが、僕自身は何も怖くなかった。何故ならエロゲとネットとオタク仲間のいる部活動があったから。建前ではコンピュータ部だったが顧問が放置主義だったため、何でもアリの文化系男子だけが集まるオタク天国だった。僕にとっては濃厚な時間でありオタクとしての出発点でもある。マンガやアニメへの開眼、コンピュータやプログラミングの知識、ネットリテラシーの習得、そしてエロゲ初体験とコミケ初参加など、何もかもが刺激的な三年間だった。
だいたいこの辺りの時期は、現実に誰かを好きになった記憶がない。中学ではクラスメイトに恋をしたこともあったが、高校ではクラスの女子になど見向きもしなかったのである。
だがまったく恋をしていなかった訳ではない。いや、熱烈に恋をしていた。もう彼女のことしか眼中になかったからこそ、その他のすべての女子がどうでもよかったともいえる。そう、あれは桜の開花を待つまだ肌寒い季節、後輩が部室に持ち込んだLeafのビジュアルノベルゲーム『To Heart』によって、そういえば僕には「温厚で可愛らしくて、面倒見が良く、家事が得意で、毎朝起こしに来てくれる同級生で幼馴染の女の子」がいたんだっけ、という前世に封印されし古えの記憶を呼び覚ましたのである。僕の濃厚な精神活動の幕開けであった。
世間一般ではマルチの方が人気だったが、ロリロリドジっ子メイドロボなんかどうでもよかった。家庭的で世話好きで地味めの美少女でいつでも浩之ちゃんを立ててくれる神岸あかりという女の子は何もかもが僕のツボだったのである。
ところがこのあかりという小娘、生半可な攻略では落ちない。落ちる気配がない。何度雅史とのホモエンディングを迎えたことか。エッチなゲームであるはずなのにちっとも色めきだったことが起こらず、くわえて最後に男から「僕たち、ずっと友達だよね」と言われる僕の気持ちがわかるだろうか。このMOBめが!お前に用は無いわっ!! そう、このゲームは幼馴染でメインヒロインの神岸あかりこそが最難関キャラなのである。
基本的に兄妹みたいな間柄の上に主人公は鈍感&あかりは想いを秘めるタイプなので、恋人同士になるためにまずはこの意識をブチ壊す必要がある。ポイントは二つ。まず後輩と親しくなって「藤田先輩は神岸先輩と付き合ってるんですか?」と聞かれること。もう一つはスポーツ万能でルックスも良いクラスのイケメン矢島に「あかりとの仲を取り持って欲しい」と懇願されることである。
「短い髪形の方が好みだ」と浩之ちゃんが言えば次の日に自分で髪を切ってショートカットにしてくるあかりのことだ。浩之ちゃんのことが嫌いなわけがない。だがここでは鈍感な浩之ちゃん故に、イケメン矢島とあかりとの仲を取り持つか否か選択肢が現れるのである。まぁこのイベントが発生すること自体は攻略が順調だと言える(この後あかりが風邪を引いてくれないとホモエンディングなので予断は許さないが)ので、大喜びで矢島を突っぱねるだろう。
僕も矢島イベントが発生したことに部室のパソコンの前で狂喜乱舞していた。もうすぐ下校時間だし一刻も早くあかりとチュッチュしたいが為にマウスを連打しテキストを飛ばしていたところ、あろうことか矢島の依頼にOKする選択肢を選んでしまったのである。よく読んでみると「俺たち付き合ってる訳じゃないし、イケメン矢島と付き合った方があかりは幸せなんじゃないか」とかワケのわからない言葉を浩之ちゃんが発していた。え?え?何コレ?
気が付けば僕は教室からあかりを呼び出し、渡り廊下で二人っきりになっていた。あかりはいつもと違う雰囲気を察して頬を赤らめ、無言で緊張した面持ち。さすがの僕でも、あかりは主人公の告白に対して心の準備をしていることはわかる。で、そこで僕が発した言葉「お前、矢島と付き合え」
「気付いてくれてると、思ってたのにな…」あかりが発した、失望の言葉を僕は一生涯忘れることが出来ない。うああああああああああああああごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい。涙を必死に堪え、蔑んだ目をする彼女を前に僕はただ謝ることしか出来なかった。その日からしばらくはあかりへの罪悪感に嘖まれ、布団にうずくまり、ゲームを再開出来なかった。セーブをやり直すことは出来ても、あの泣いて怒るあかりの鬼の形相を忘れることは出来ない。
とまぁ、明らかにあかりシナリオに悩殺され、あかりとの疑似恋愛に明け暮れた日々であった。原作をプレイするだけでなく、ネットであかりのイラストCGを収集したり、二次創作のネット小説を渉猟したりした。それでも飽き足らずあかりへの想いが迸っていた僕は、自分であかりの絵を描くようになり、その絵をアイロンプリントした自作Tシャツでオフ会に行ったり、あかりと一緒に同じ大学に進学して同棲生活を始めたという設定の小説を書いてネットで公開したりしていたのである。あかりファン同士で熱く語り合ったり、二次創作を公開し合ったりもしていた。あの頃はちっとも恥ずかしいなんて感情はなく、何の疑問も感じずひたすら悦に浸っていたと思う。若気の至りというやつである。
今思えばファン同士で「俺の嫁だ」と対立するようなこともなかった。あかりは皆で共有すべき彼女であり、人類の共有財産だと本気で思っていたのかもしれない。まぁ、現実に彼女なんかいなくてもその時は楽しかったし、みんな二次元という魔法を使いこなせればそれで幸せになれると思っていたのである。
教室の中で浮いている自覚はあったが、僕自身は何も怖くなかった。何故ならエロゲとネットとオタク仲間のいる部活動があったから。建前ではコンピュータ部だったが顧問が放置主義だったため、何でもアリの文化系男子だけが集まるオタク天国だった。僕にとっては濃厚な時間でありオタクとしての出発点でもある。マンガやアニメへの開眼、コンピュータやプログラミングの知識、ネットリテラシーの習得、そしてエロゲ初体験とコミケ初参加など、何もかもが刺激的な三年間だった。
だいたいこの辺りの時期は、現実に誰かを好きになった記憶がない。中学ではクラスメイトに恋をしたこともあったが、高校ではクラスの女子になど見向きもしなかったのである。
だがまったく恋をしていなかった訳ではない。いや、熱烈に恋をしていた。もう彼女のことしか眼中になかったからこそ、その他のすべての女子がどうでもよかったともいえる。そう、あれは桜の開花を待つまだ肌寒い季節、後輩が部室に持ち込んだLeafのビジュアルノベルゲーム『To Heart』によって、そういえば僕には「温厚で可愛らしくて、面倒見が良く、家事が得意で、毎朝起こしに来てくれる同級生で幼馴染の女の子」がいたんだっけ、という前世に封印されし古えの記憶を呼び覚ましたのである。僕の濃厚な精神活動の幕開けであった。
世間一般ではマルチの方が人気だったが、ロリロリドジっ子メイドロボなんかどうでもよかった。家庭的で世話好きで地味めの美少女でいつでも浩之ちゃんを立ててくれる神岸あかりという女の子は何もかもが僕のツボだったのである。
ところがこのあかりという小娘、生半可な攻略では落ちない。落ちる気配がない。何度雅史とのホモエンディングを迎えたことか。エッチなゲームであるはずなのにちっとも色めきだったことが起こらず、くわえて最後に男から「僕たち、ずっと友達だよね」と言われる僕の気持ちがわかるだろうか。このMOBめが!お前に用は無いわっ!! そう、このゲームは幼馴染でメインヒロインの神岸あかりこそが最難関キャラなのである。
基本的に兄妹みたいな間柄の上に主人公は鈍感&あかりは想いを秘めるタイプなので、恋人同士になるためにまずはこの意識をブチ壊す必要がある。ポイントは二つ。まず後輩と親しくなって「藤田先輩は神岸先輩と付き合ってるんですか?」と聞かれること。もう一つはスポーツ万能でルックスも良いクラスのイケメン矢島に「あかりとの仲を取り持って欲しい」と懇願されることである。
「短い髪形の方が好みだ」と浩之ちゃんが言えば次の日に自分で髪を切ってショートカットにしてくるあかりのことだ。浩之ちゃんのことが嫌いなわけがない。だがここでは鈍感な浩之ちゃん故に、イケメン矢島とあかりとの仲を取り持つか否か選択肢が現れるのである。まぁこのイベントが発生すること自体は攻略が順調だと言える(この後あかりが風邪を引いてくれないとホモエンディングなので予断は許さないが)ので、大喜びで矢島を突っぱねるだろう。
僕も矢島イベントが発生したことに部室のパソコンの前で狂喜乱舞していた。もうすぐ下校時間だし一刻も早くあかりとチュッチュしたいが為にマウスを連打しテキストを飛ばしていたところ、あろうことか矢島の依頼にOKする選択肢を選んでしまったのである。よく読んでみると「俺たち付き合ってる訳じゃないし、イケメン矢島と付き合った方があかりは幸せなんじゃないか」とかワケのわからない言葉を浩之ちゃんが発していた。え?え?何コレ?
気が付けば僕は教室からあかりを呼び出し、渡り廊下で二人っきりになっていた。あかりはいつもと違う雰囲気を察して頬を赤らめ、無言で緊張した面持ち。さすがの僕でも、あかりは主人公の告白に対して心の準備をしていることはわかる。で、そこで僕が発した言葉「お前、矢島と付き合え」
「気付いてくれてると、思ってたのにな…」あかりが発した、失望の言葉を僕は一生涯忘れることが出来ない。うああああああああああああああごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさいごめんなさい。涙を必死に堪え、蔑んだ目をする彼女を前に僕はただ謝ることしか出来なかった。その日からしばらくはあかりへの罪悪感に嘖まれ、布団にうずくまり、ゲームを再開出来なかった。セーブをやり直すことは出来ても、あの泣いて怒るあかりの鬼の形相を忘れることは出来ない。
とまぁ、明らかにあかりシナリオに悩殺され、あかりとの疑似恋愛に明け暮れた日々であった。原作をプレイするだけでなく、ネットであかりのイラストCGを収集したり、二次創作のネット小説を渉猟したりした。それでも飽き足らずあかりへの想いが迸っていた僕は、自分であかりの絵を描くようになり、その絵をアイロンプリントした自作Tシャツでオフ会に行ったり、あかりと一緒に同じ大学に進学して同棲生活を始めたという設定の小説を書いてネットで公開したりしていたのである。あかりファン同士で熱く語り合ったり、二次創作を公開し合ったりもしていた。あの頃はちっとも恥ずかしいなんて感情はなく、何の疑問も感じずひたすら悦に浸っていたと思う。若気の至りというやつである。
今思えばファン同士で「俺の嫁だ」と対立するようなこともなかった。あかりは皆で共有すべき彼女であり、人類の共有財産だと本気で思っていたのかもしれない。まぁ、現実に彼女なんかいなくてもその時は楽しかったし、みんな二次元という魔法を使いこなせればそれで幸せになれると思っていたのである。
□そして焦りが爆発する
レンアイというものが漠然としていた高校までとは打って変わって、大学生になると急に周囲で現実感を帯び始めた。高校まで浮いた話のなかった男友達もいつの間にか彼女を作っていたり、あるいは仲の良い女友達が出来ていてフランクに駄弁ったり遊びに行ったりしていたのである。
特に僕が入居していた学生寮では先輩方のリア充臭が物凄く、彼女がいて当たり前、連れ込んで当たり前みたいな雰囲気だった。男子寮だが廊下で女の子とすれ違うなんてザラで、昼も夜も喋り声や笑い声、キャッキャウフフが漏れまくっていた。トイレに行けば女の子が酔い潰れていたり、部屋に戻れば先輩の部屋と間違えた女の子が酔い潰れていたりして、その度に先輩に知らせに行くのが日常茶飯事だった。
そんななか、初秋の頃に1年生が食堂に集められた。怖い先輩方が話すには「我が寮では秋に寮祭を執り行う。いつもの飲み会とは異なり、年に一度女性のお客様を寮に呼ぶことが許される特別なイベントだ。1年は全員必ず2〜3人女友達を連れて来い。呼べなかったら殺す。肋骨3本は覚悟しろ。わかったな!」ということだった。
この寮にそういうルールが存在することは予め耳にしていた。しかし僕はというと、とてもじゃないが気軽に誘えるような女の子は皆無だったのである。そもそも小学生の頃から、中学、高校、大学に至るまで、現実に女友達なんて作れなかった。気が付けば僕は同世代の女の子と会話することすら極度に緊張するような、コミュニケーションスキルゼロの男になっていたのである。声が裏返って笑われたり、空気の読めない発言で白けたりでもしたらと思うと、恥ずかしくてどうしても女の子に話しかける最初の一歩が踏み出せなかった。
一方で寮の先輩方は本気で怖かった。暴力を振るわれるというワケではなかったが、体育会系というか昭和のバンカラ気質というか寮には独特の秩序があり、先輩に可愛がってもらえればメシや酒を奢ってもらったり様々な遊びを教わったりする反面、筋が通らないことをすれば寮内での立場が悪くなったり発言権が無くなったりした。それに今回は女性の招待客を呼べなければみんなに迷惑を掛けるだけでなく「大学生にもなって、女の子一人誘えないのか」という周囲の白い目が待っている。逃げ道は残されていなかった。
寮祭が近づくにつれて、僕は暗澹たる気持ちになった。毎日のように先輩から「早く声を掛けないと相手の予定が埋まるぞ」「1人だけで誘うと相手も抵抗あるから、女友達グループをまとめて誘え」「俺らのせいにしていいから『怖い先輩に殺されるから来てくれ』と泣き落とししてでも連れて来い」と口酸っぱくけしかけられた。
たぶん寮としてもこれは初心で奥手な1年生のコミュニケーションスキルを強制的に伸ばすための伝統的な通過儀礼なのだろう。寮祭そのものよりも1年生への荒療治がメインなのだ。だが当時の僕にとっては拷問以外の何者でもなかった。
結局のところ、1年生で僕だけが女の子を連れて来れなかった。正確に言えば僕は誰一人女の子に声を掛けることすら出来なかったのである。寮祭の前夜、比較的面倒を見てくれた先輩に呼ばれ、慰めの言葉でも掛けてくれるのかなと思いきや「ヘラヘラしてんじゃねぇ。なんで連れてこなかった」と凄まれた。胃が痛いどころの騒ぎではなく、背筋が凍り心臓がきつく締めつけられた。次の日、たくさん女の子がいる飲み会だったというのに僕は完全に放心し、生きた心地がしなかった。
それ以降、僕は自分自身がどういう状態なのかを改めて認識するところとなった。いや、薄々気付いていた。気が付かないフリをしていたのだ。周囲に彼女が出来たり、女の子と遊びに行ったりコンパに行ったりしているなか、僕が女の子と付き合うのはまだ早いのだと、ずっとそう思い続けてきた。いつかはわからないが、いずれ僕にもそういうイベントが自然に発生するのだろうと漠然と考えていたのである。
だが気付いてしまった。もうとっくに遅かったのだと。僕は女の子と付き合うどころか話をすることすら出来ないような、自分の殻に閉じこもった人間になっていた。桜木花道は中学時代に50人の女性に告白して全員にフラれていたが、僕は大学生になってからも一度もフラれたことがなかった。一度も告白してないのだから当たり前だ。要は努力もチャレンジもしないまま大人になり、そして失敗することに耐えられない脆弱な自尊心を持ってしまったのである。このような姿勢では今後もずっと色恋沙汰なんてないだろう。僕のことをわかってくれる女の子なんて今まで現れなかったのだから、これからも現れることはないだろう。そうハッキリわかってしまった。その瞬間、僕の心は絶望に支配され、自我が崩壊してしまった。
大げさに聞こえるかもしれないが、本来なら10代のうちに何度も転んでおくべきだったのだ。何度も痛い思いを経験しておけば、次にまたチャレンジする元気が湧いてきただろう。この程度では潰れないというような自分自身を信じる力も持てたかもしれない。その試行錯誤をすべき貴重な10年間をドブに捨ててしまったのだ。10年という時間を無駄にしたという後悔の念は重い。重過ぎる。その重さに僕は耐えられなかった。取り返しのつかないことをしてしまったと強烈に自分自身を責め、自分のダメさに打ちのめされ、僕は自分の生きてる意味がわからなくなった。
僕自身自分を肯定出来ないまま時間だけが過ぎ、2年生になってから再び寮祭の季節が到来した。僕は後輩の1年生に対して「女友達を連れて来い」とは言えなかった。僕自身去年のノルマを再び課される立場だった。そして去年以上に極度のストレスを感じるまま誰も呼べずに寮祭の日を迎え、さらに自分自身を責めた。
2年生時の12月24日、何の予定もないまま寮に帰ると寮の玄関に女の子のブーツやミュールが何足も脱いで置いてあったのを今でも鮮明に憶えている。きっと寮のみんなが部屋に連れ込んでよろしくやっているのだろう。もうそれを見ただけで吐き気が止まらなかった。本気で死にたくなり、自殺したい気持ちを必死で踏みとどまる夜が続いた。いつしか心療内科に通うようになっていた。
年が明けて気持ちの波が落ち着くようになると、心の中の絶望を咀嚼するように「恋愛は諦めよう」「人生に期待するな」というような諦観を持つようになっていた。期待するから苦しくなるのだ。あんな自己否定の気持ちと対峙するくらいなら、心の平穏を望むという気持ちが芽生えていた。こんな情けない決心するなんて悔しくないわけがないし涙が止まらなかったが、とにかく死にたくなかったのである。僕は生きるために恋愛を諦めたのだった。
特に僕が入居していた学生寮では先輩方のリア充臭が物凄く、彼女がいて当たり前、連れ込んで当たり前みたいな雰囲気だった。男子寮だが廊下で女の子とすれ違うなんてザラで、昼も夜も喋り声や笑い声、キャッキャウフフが漏れまくっていた。トイレに行けば女の子が酔い潰れていたり、部屋に戻れば先輩の部屋と間違えた女の子が酔い潰れていたりして、その度に先輩に知らせに行くのが日常茶飯事だった。
そんななか、初秋の頃に1年生が食堂に集められた。怖い先輩方が話すには「我が寮では秋に寮祭を執り行う。いつもの飲み会とは異なり、年に一度女性のお客様を寮に呼ぶことが許される特別なイベントだ。1年は全員必ず2〜3人女友達を連れて来い。呼べなかったら殺す。肋骨3本は覚悟しろ。わかったな!」ということだった。
この寮にそういうルールが存在することは予め耳にしていた。しかし僕はというと、とてもじゃないが気軽に誘えるような女の子は皆無だったのである。そもそも小学生の頃から、中学、高校、大学に至るまで、現実に女友達なんて作れなかった。気が付けば僕は同世代の女の子と会話することすら極度に緊張するような、コミュニケーションスキルゼロの男になっていたのである。声が裏返って笑われたり、空気の読めない発言で白けたりでもしたらと思うと、恥ずかしくてどうしても女の子に話しかける最初の一歩が踏み出せなかった。
一方で寮の先輩方は本気で怖かった。暴力を振るわれるというワケではなかったが、体育会系というか昭和のバンカラ気質というか寮には独特の秩序があり、先輩に可愛がってもらえればメシや酒を奢ってもらったり様々な遊びを教わったりする反面、筋が通らないことをすれば寮内での立場が悪くなったり発言権が無くなったりした。それに今回は女性の招待客を呼べなければみんなに迷惑を掛けるだけでなく「大学生にもなって、女の子一人誘えないのか」という周囲の白い目が待っている。逃げ道は残されていなかった。
寮祭が近づくにつれて、僕は暗澹たる気持ちになった。毎日のように先輩から「早く声を掛けないと相手の予定が埋まるぞ」「1人だけで誘うと相手も抵抗あるから、女友達グループをまとめて誘え」「俺らのせいにしていいから『怖い先輩に殺されるから来てくれ』と泣き落とししてでも連れて来い」と口酸っぱくけしかけられた。
たぶん寮としてもこれは初心で奥手な1年生のコミュニケーションスキルを強制的に伸ばすための伝統的な通過儀礼なのだろう。寮祭そのものよりも1年生への荒療治がメインなのだ。だが当時の僕にとっては拷問以外の何者でもなかった。
結局のところ、1年生で僕だけが女の子を連れて来れなかった。正確に言えば僕は誰一人女の子に声を掛けることすら出来なかったのである。寮祭の前夜、比較的面倒を見てくれた先輩に呼ばれ、慰めの言葉でも掛けてくれるのかなと思いきや「ヘラヘラしてんじゃねぇ。なんで連れてこなかった」と凄まれた。胃が痛いどころの騒ぎではなく、背筋が凍り心臓がきつく締めつけられた。次の日、たくさん女の子がいる飲み会だったというのに僕は完全に放心し、生きた心地がしなかった。
それ以降、僕は自分自身がどういう状態なのかを改めて認識するところとなった。いや、薄々気付いていた。気が付かないフリをしていたのだ。周囲に彼女が出来たり、女の子と遊びに行ったりコンパに行ったりしているなか、僕が女の子と付き合うのはまだ早いのだと、ずっとそう思い続けてきた。いつかはわからないが、いずれ僕にもそういうイベントが自然に発生するのだろうと漠然と考えていたのである。
だが気付いてしまった。もうとっくに遅かったのだと。僕は女の子と付き合うどころか話をすることすら出来ないような、自分の殻に閉じこもった人間になっていた。桜木花道は中学時代に50人の女性に告白して全員にフラれていたが、僕は大学生になってからも一度もフラれたことがなかった。一度も告白してないのだから当たり前だ。要は努力もチャレンジもしないまま大人になり、そして失敗することに耐えられない脆弱な自尊心を持ってしまったのである。このような姿勢では今後もずっと色恋沙汰なんてないだろう。僕のことをわかってくれる女の子なんて今まで現れなかったのだから、これからも現れることはないだろう。そうハッキリわかってしまった。その瞬間、僕の心は絶望に支配され、自我が崩壊してしまった。
大げさに聞こえるかもしれないが、本来なら10代のうちに何度も転んでおくべきだったのだ。何度も痛い思いを経験しておけば、次にまたチャレンジする元気が湧いてきただろう。この程度では潰れないというような自分自身を信じる力も持てたかもしれない。その試行錯誤をすべき貴重な10年間をドブに捨ててしまったのだ。10年という時間を無駄にしたという後悔の念は重い。重過ぎる。その重さに僕は耐えられなかった。取り返しのつかないことをしてしまったと強烈に自分自身を責め、自分のダメさに打ちのめされ、僕は自分の生きてる意味がわからなくなった。
僕自身自分を肯定出来ないまま時間だけが過ぎ、2年生になってから再び寮祭の季節が到来した。僕は後輩の1年生に対して「女友達を連れて来い」とは言えなかった。僕自身去年のノルマを再び課される立場だった。そして去年以上に極度のストレスを感じるまま誰も呼べずに寮祭の日を迎え、さらに自分自身を責めた。
2年生時の12月24日、何の予定もないまま寮に帰ると寮の玄関に女の子のブーツやミュールが何足も脱いで置いてあったのを今でも鮮明に憶えている。きっと寮のみんなが部屋に連れ込んでよろしくやっているのだろう。もうそれを見ただけで吐き気が止まらなかった。本気で死にたくなり、自殺したい気持ちを必死で踏みとどまる夜が続いた。いつしか心療内科に通うようになっていた。
年が明けて気持ちの波が落ち着くようになると、心の中の絶望を咀嚼するように「恋愛は諦めよう」「人生に期待するな」というような諦観を持つようになっていた。期待するから苦しくなるのだ。あんな自己否定の気持ちと対峙するくらいなら、心の平穏を望むという気持ちが芽生えていた。こんな情けない決心するなんて悔しくないわけがないし涙が止まらなかったが、とにかく死にたくなかったのである。僕は生きるために恋愛を諦めたのだった。
■Chapter.2 キミがいることで、自分の存在を感じられる
□絶望に効くクスリ
大学生になってから僕は、緊急避難的に恋愛に対する希望を捨て、絶望を受け入れた。とにかく自己評価がすごく低い状態で、真面目に状況を打開しようと思えば、生きるのに最低限必要な自尊心さえズタズタに引き裂かれることは目に見えていた。それだけ自信を失い意気消沈していたのだ。
恋愛に幻想を抱いていたことは確かだが、やはりそれでも女の子に僕を認めて欲しかった。女の子に認めてもらえてそこで初めて僕は生きることが出来て、僕が何者なのか自分でわかるような気がしていたのだ。
それが叶わないとなると、自分が何の為に生きているのかわからなかった。彼女が出来ることが人生の全てではないけれど、僕は別に何かの特技があるわけでも誇れるところがあるわけでもなかった。役立たずで、良いところ、優れているところが僕自身見出せなくて、自分で自分を認めることが出来なかった。自分で自分に魅力を感じられない以上、僕が誰かから認められたり、頼られたり、好かれたりするわけがないと思っていた。もう悪循環だったのだ。
もちろんこのままではいけないとも考えていた。どこかで負の連鎖は断ちきらなければいつか再び絶望と対峙したときに負けてしまう。しかし、取っ掛かりは何もなかった。サークルや課外活動やアルバイトなど、いろいろなところに積極的に首を突っ込んで、試して、踠いて、そして何度も上手くいかない思いをして、すっかり自尊心が疲弊してしまったのである。僕は人並みの幸せを手に入れようとするとすごく苦しい人生になるのだと悟らざるを得なかった。いっそのこと死んでしまいたかった。でも諦めきれない。でももう無理っぽい。なんども精神状態を躁に鬱にバウンドさせながら、結局は泣きながら絶望を受け入れる。何もかも冷めた状態になっていったのだろう。もはや疲れ果て、涙も枯れてしまった。こんな精神状態ではどうしようもないし、僕が生きてる意味なんてきっと無いのだ、どうせ残りの人生は余生なんだと割り切って、粛々と目の前の雑務をこなすようになっていった。
だが皮肉なことに、この「何も期待しない冷めた感情」になると、次第に周囲から「年の割に大人っぽいよね」「落ち着きがある」「いつも冷静でカッコいい」と言われ始めるようになったのである。女の子に認めてもらえなかったから絶望して、絶望したから人生の消化試合を淡々と進めていたはずなのに、いつの間にか女の子からも話しかけてもらえるようになっていた。こちらからは聞いていない(聞きたくても聞く勇気など無かった)のにメアドや電話番号を貰うようになり、向こうからも遊びに誘われるようにもなったのだ。
僕には何が起こっているか意味がわからなかった。希望などとっくに捨ててしまったし心は冷えきっていたので、それらのイベントに関しても目の前の雑務同様粛々とこなしていた。余生を送る僕に対して天からの餞別か何かだと思っていた。期待すればきっと裏切られる。僕は死にたくなかったのである。
恋愛に幻想を抱いていたことは確かだが、やはりそれでも女の子に僕を認めて欲しかった。女の子に認めてもらえてそこで初めて僕は生きることが出来て、僕が何者なのか自分でわかるような気がしていたのだ。
それが叶わないとなると、自分が何の為に生きているのかわからなかった。彼女が出来ることが人生の全てではないけれど、僕は別に何かの特技があるわけでも誇れるところがあるわけでもなかった。役立たずで、良いところ、優れているところが僕自身見出せなくて、自分で自分を認めることが出来なかった。自分で自分に魅力を感じられない以上、僕が誰かから認められたり、頼られたり、好かれたりするわけがないと思っていた。もう悪循環だったのだ。
もちろんこのままではいけないとも考えていた。どこかで負の連鎖は断ちきらなければいつか再び絶望と対峙したときに負けてしまう。しかし、取っ掛かりは何もなかった。サークルや課外活動やアルバイトなど、いろいろなところに積極的に首を突っ込んで、試して、踠いて、そして何度も上手くいかない思いをして、すっかり自尊心が疲弊してしまったのである。僕は人並みの幸せを手に入れようとするとすごく苦しい人生になるのだと悟らざるを得なかった。いっそのこと死んでしまいたかった。でも諦めきれない。でももう無理っぽい。なんども精神状態を躁に鬱にバウンドさせながら、結局は泣きながら絶望を受け入れる。何もかも冷めた状態になっていったのだろう。もはや疲れ果て、涙も枯れてしまった。こんな精神状態ではどうしようもないし、僕が生きてる意味なんてきっと無いのだ、どうせ残りの人生は余生なんだと割り切って、粛々と目の前の雑務をこなすようになっていった。
だが皮肉なことに、この「何も期待しない冷めた感情」になると、次第に周囲から「年の割に大人っぽいよね」「落ち着きがある」「いつも冷静でカッコいい」と言われ始めるようになったのである。女の子に認めてもらえなかったから絶望して、絶望したから人生の消化試合を淡々と進めていたはずなのに、いつの間にか女の子からも話しかけてもらえるようになっていた。こちらからは聞いていない(聞きたくても聞く勇気など無かった)のにメアドや電話番号を貰うようになり、向こうからも遊びに誘われるようにもなったのだ。
僕には何が起こっているか意味がわからなかった。希望などとっくに捨ててしまったし心は冷えきっていたので、それらのイベントに関しても目の前の雑務同様粛々とこなしていた。余生を送る僕に対して天からの餞別か何かだと思っていた。期待すればきっと裏切られる。僕は死にたくなかったのである。
□キミが現れた
今までの流れからすると唐突だが、僕がカメラを持ち始めたのはこの頃からである。前述の通り僕は大分精神状態が病んでいた。ぶっちゃけた話そもそも人生に意味なんか無いのである。僕が生きる意味は──なんて難しいことを考えるから精神を病むのだ。高尚な悩みには思いっきり低俗なことをすべきである。全裸になってパンを尻にはさみ、右手の指を鼻の穴に入れ、左手でボクシングをしながら「いのちをだいじに」と叫べば人生が無意味だということくらいすぐに気が付くだろう。
かくいう僕も「彼女が出来ないから死にたい」「やっぱり死にたくない」なんて無意味な葛藤に時間を費やすくらいなら、さっさと可愛い女の子のコスプレ姿を撮影してキャッキャウフフしていた方がきっと楽しいという至極当たり前の事実に気が付き、全ての悩みをいったん棚に上げた。
たまたまエロサイトを巡回していたところ、何故か撮影会のサイトに行き当たり、コスプレ撮影会なるものがこの世に存在するのを知ったことがきっかけだった。人生に疲れたと考えること自体に疲れていた僕は、もう何もかもがどうでもいいからストレス解消に参加しちゃえと思い、エイヤと参加申込をしたのである。
その時点ではカメラなどほとんど触ったことはなく、撮影の知識もほぼ皆無だった。普段の僕だったら「ある程度撮影の技術を身に付けて、ちゃんとしたカメラを買ってからそういう場に参加しよう」と構えてしまっただろうが、そのときは「勢いで申し込んじゃったから最悪カメラ持って来りゃ何でもいいじゃん」と開き直っていた。それがよかったのかどうかわからないが、かなり気楽な心持ちで撮影会に行ったのである。
いざ撮影会に来てみると、30代40代のオジサンばかりだった。そういえばそうだよね。写真が趣味の時点で何万円もするカメラを持っているわけだから、僕みたいなしょぼいコンパクトカメラを持った20歳前後の男の子なんか他にいるわけないよね。少し凹みつつも主催の挨拶が始まり、そして出演モデルの女の子たちがやってきた。
うわ!めっちゃ可愛い!物凄い美少女ばかりだ…!最初の印象はそうだった。普段であれば下々の情けない僕なんかとは絶対に接点などなさそうな、綺麗で天使のような女の人たちばかりだった。やっぱり来て良かった。とてもじゃないが自力でここまで綺麗な絶世の美女と接点を持てるとは思わなかったのである。殿上人に接見するような気分で僕は下手クソなりにシャッターを切りまくり、そこで初めて女の子を撮る楽しさを知った。ストレスを一時的にでも忘れるため、という後ろ向きの参加理由は吹っ飛んでいたのである。撮影会が終わるとすぐさま貯金をはたいて最新のデジカメを買った。
そうして2回目、3回目と撮影会に参加していくうちに、出演モデルさんとも参加カメラマンさんとも次第に顔見知りになっていった。特にこんなに可愛い女の子が僕の顔と名前を覚えてくれて、そして気さくに笑顔で話しかけてくれることが僕にとっては生まれて初めての体験で、どんどん撮影というものに熱中していったのである。
一方で撮影会には明確なルールも存在した。モデルの女の子とはきちんと距離を置かなければならないというものだ。セクハラやストーキングはもちろん、個人的に仲良くなりたくてナンパしたり、連絡先を聞いたりすることはタブーだった。モデルの女の子はあくまで被写体として撮影会に来ているのであり、出会いを求めているわけではない。この辺のことは結構厳しく取り締まっており、違反者はその撮影会で参加禁止になるだけでなく、他の撮影会にも通知が行き渡り全ての場で参加禁止という措置が取られていた。ついでに言うと、その手の情報はすぐ周囲に広まった。モデルに触れるべからず、連絡先を聞くべからず、付きまとうべからずは撮影会鉄の掟だったのである。
だが僕からすると、そのルールがあってもなくても僕の行動は何も変わらなかった。そもそも自己評価がすごく低かった僕にとっては、美人の女性は最初から触れることなど許されない絶対的に高貴な存在で、まして住所や連絡先を聞くなんてことは最初から思い付かなかったのである。高嶺の花をファインダー越しに謁見するだけで僕は十分に幸福だったのだ。
そんななか、知り合いのモデルさんから「愛しのカメラマンさんへ(はぁと」というメールが届いた。パソコン用の公開アドレスとはいえ、可愛い女の子が僕なんかにメールを送ってくれるとは夢にも思わなかったのである。ひどく驚いた。さらにビックリしたのは、なんと僕に個人的に写真を撮って欲しいという撮影依頼だったのである。僕なんかでいいのだろうかと恐縮しつつ、お気に入りのモデルさんからのお願いだったので二つ返事で承諾したのだった。
彼女はウェブサイトに掲載する写真が欲しいので、最新のデジカメを持っている僕に撮って欲しいということだった。何度かやり取りとした後、週末に公園で待ち合わせてミニ撮影会をすることになったのである。
しかし、今回はちゃんと場を仕切る主催の人がいない。そして詳しくない公園だったのでアバウトな集合場所しか決められない。さすがに現地で合流出来なかったらとどうしようと不安だったので、迷った揚げ句、念のためと称して彼女のパソコン用メールアドレスに一方的に僕の携帯の連絡先を伝えた。
こちらの連絡先は送ったものの、それを使えば僕に電話番号や携帯のメールアドレスを知られることになる。だから彼女からメールや電話をしてくることはないだろうと思っていた。しかし、予想に反して彼女からは普通に「少し遅れます」という電話が着たので僕は物凄く驚いた。
この「可愛い女の子と二人きりで会う」というシチュエーションは僕にとって生まれて初めてのことだった。それでも特に臆したりせずに普段通り振る舞うことが出来たのは、やはり心の片隅で「恋愛は諦める」「人生に期待するな」を強く意識していたからである。僕はルサンチマンに浸り、どこか冷めていた。だがそれでも女の子に撮影を頼まれ、頼りにされてることは嬉しかった。
撮影が終わると「一緒にゴハンでもどう?」と彼女に誘われた。僕は今の状況が本当に信じられなかった。僕は未だかつて、女の子と二人っきりで食事の出来る店に入ったことがなかったのである。夢でも見ているのだろうかと思わずにはいられなかった。そもそもコミュニケーションスキルが皆無の男であり、今まで全然女の子とまともに会話すら出来なかった僕が、とびきり可愛い女の子と二人きりでいるのである。少しずつ、冷たくなった心が温まり始めていた。
二人で食事をしながら僕は正直に自分の思うところを吐露した。気が付いたら「撮影会ではモデルさんが絶対的に高貴なポジションの存在で、下々の僕ら(カメラマン)は接触の許されぬ存在だと思っていた。だから今こうして二人きりで食事をしていることが未だに信じられない。天から下々のところに下りてきたとかそういう感覚。というか下りてきていいの?」みたいなことを話していたのだ。共通の話題があり向こうも好意的だったお陰か、初めて可愛い女の子と二人きりになったわりには話は弾んで数時間はお喋りしていた。当時のレシートは今も記念に取ってある。
彼女の存在は僕に多大なる影響を与えた。個人的な撮影を頼まれただけとはいえ、僕にとっては生まれて初めて女の子から必要とされた瞬間だったのである。それまで僕のことを誰かに認めて欲しくて、承認を渇望し、女の子との関係性に飢えていた。自分が役に立たない、ダメ人間、死んだ方がマシ、でも仕方ないよね貴重な思春期を無駄に過ごしたのだから、と絶望を受け入れ静かに人生の敗戦処理をしていた。その荒んだ心の穴を埋めるように可愛い女の子から役割を与えられ、役に立つことが出来て、そして評価されたのである。
僕はそこで初めて僕を認めてもらえた、肯定してもらえたと思えるようになった。死にたい気持ちを押し殺すように、ずっと冷めた心を持ち続けていた僕は「この世で生きていてもいいよ」と彼女から生きることを許された気がしたのである。
極端に見えるかも知れない。しかし、可愛い女の子から何かを頼まれる、頼られるということは、言い方を変えれば彼女から何かを要求・期待されているわけであり、その要求・期待の裏には「死ぬことは許さん、生きてそれをやれ」が含まれているのである。振り返ってみれば、それまで異性から何かを依頼されたり期待されたりするような社会との関わり方をしたことが無かった。
もちろん僕の勝手な解釈だが、彼女からの「死ぬことは許さん、生きてそれをやれ」のメッセージがとても嬉しかった。彼女はきっと知らないだろうが僕にとっては命の恩人なのだ。キモイと思われようが、身分違いだろうが、僕は彼女のことを好きになっていた。
かくいう僕も「彼女が出来ないから死にたい」「やっぱり死にたくない」なんて無意味な葛藤に時間を費やすくらいなら、さっさと可愛い女の子のコスプレ姿を撮影してキャッキャウフフしていた方がきっと楽しいという至極当たり前の事実に気が付き、全ての悩みをいったん棚に上げた。
たまたまエロサイトを巡回していたところ、何故か撮影会のサイトに行き当たり、コスプレ撮影会なるものがこの世に存在するのを知ったことがきっかけだった。人生に疲れたと考えること自体に疲れていた僕は、もう何もかもがどうでもいいからストレス解消に参加しちゃえと思い、エイヤと参加申込をしたのである。
その時点ではカメラなどほとんど触ったことはなく、撮影の知識もほぼ皆無だった。普段の僕だったら「ある程度撮影の技術を身に付けて、ちゃんとしたカメラを買ってからそういう場に参加しよう」と構えてしまっただろうが、そのときは「勢いで申し込んじゃったから最悪カメラ持って来りゃ何でもいいじゃん」と開き直っていた。それがよかったのかどうかわからないが、かなり気楽な心持ちで撮影会に行ったのである。
いざ撮影会に来てみると、30代40代のオジサンばかりだった。そういえばそうだよね。写真が趣味の時点で何万円もするカメラを持っているわけだから、僕みたいなしょぼいコンパクトカメラを持った20歳前後の男の子なんか他にいるわけないよね。少し凹みつつも主催の挨拶が始まり、そして出演モデルの女の子たちがやってきた。
うわ!めっちゃ可愛い!物凄い美少女ばかりだ…!最初の印象はそうだった。普段であれば下々の情けない僕なんかとは絶対に接点などなさそうな、綺麗で天使のような女の人たちばかりだった。やっぱり来て良かった。とてもじゃないが自力でここまで綺麗な絶世の美女と接点を持てるとは思わなかったのである。殿上人に接見するような気分で僕は下手クソなりにシャッターを切りまくり、そこで初めて女の子を撮る楽しさを知った。ストレスを一時的にでも忘れるため、という後ろ向きの参加理由は吹っ飛んでいたのである。撮影会が終わるとすぐさま貯金をはたいて最新のデジカメを買った。
そうして2回目、3回目と撮影会に参加していくうちに、出演モデルさんとも参加カメラマンさんとも次第に顔見知りになっていった。特にこんなに可愛い女の子が僕の顔と名前を覚えてくれて、そして気さくに笑顔で話しかけてくれることが僕にとっては生まれて初めての体験で、どんどん撮影というものに熱中していったのである。
一方で撮影会には明確なルールも存在した。モデルの女の子とはきちんと距離を置かなければならないというものだ。セクハラやストーキングはもちろん、個人的に仲良くなりたくてナンパしたり、連絡先を聞いたりすることはタブーだった。モデルの女の子はあくまで被写体として撮影会に来ているのであり、出会いを求めているわけではない。この辺のことは結構厳しく取り締まっており、違反者はその撮影会で参加禁止になるだけでなく、他の撮影会にも通知が行き渡り全ての場で参加禁止という措置が取られていた。ついでに言うと、その手の情報はすぐ周囲に広まった。モデルに触れるべからず、連絡先を聞くべからず、付きまとうべからずは撮影会鉄の掟だったのである。
だが僕からすると、そのルールがあってもなくても僕の行動は何も変わらなかった。そもそも自己評価がすごく低かった僕にとっては、美人の女性は最初から触れることなど許されない絶対的に高貴な存在で、まして住所や連絡先を聞くなんてことは最初から思い付かなかったのである。高嶺の花をファインダー越しに謁見するだけで僕は十分に幸福だったのだ。
そんななか、知り合いのモデルさんから「愛しのカメラマンさんへ(はぁと」というメールが届いた。パソコン用の公開アドレスとはいえ、可愛い女の子が僕なんかにメールを送ってくれるとは夢にも思わなかったのである。ひどく驚いた。さらにビックリしたのは、なんと僕に個人的に写真を撮って欲しいという撮影依頼だったのである。僕なんかでいいのだろうかと恐縮しつつ、お気に入りのモデルさんからのお願いだったので二つ返事で承諾したのだった。
彼女はウェブサイトに掲載する写真が欲しいので、最新のデジカメを持っている僕に撮って欲しいということだった。何度かやり取りとした後、週末に公園で待ち合わせてミニ撮影会をすることになったのである。
しかし、今回はちゃんと場を仕切る主催の人がいない。そして詳しくない公園だったのでアバウトな集合場所しか決められない。さすがに現地で合流出来なかったらとどうしようと不安だったので、迷った揚げ句、念のためと称して彼女のパソコン用メールアドレスに一方的に僕の携帯の連絡先を伝えた。
こちらの連絡先は送ったものの、それを使えば僕に電話番号や携帯のメールアドレスを知られることになる。だから彼女からメールや電話をしてくることはないだろうと思っていた。しかし、予想に反して彼女からは普通に「少し遅れます」という電話が着たので僕は物凄く驚いた。
この「可愛い女の子と二人きりで会う」というシチュエーションは僕にとって生まれて初めてのことだった。それでも特に臆したりせずに普段通り振る舞うことが出来たのは、やはり心の片隅で「恋愛は諦める」「人生に期待するな」を強く意識していたからである。僕はルサンチマンに浸り、どこか冷めていた。だがそれでも女の子に撮影を頼まれ、頼りにされてることは嬉しかった。
撮影が終わると「一緒にゴハンでもどう?」と彼女に誘われた。僕は今の状況が本当に信じられなかった。僕は未だかつて、女の子と二人っきりで食事の出来る店に入ったことがなかったのである。夢でも見ているのだろうかと思わずにはいられなかった。そもそもコミュニケーションスキルが皆無の男であり、今まで全然女の子とまともに会話すら出来なかった僕が、とびきり可愛い女の子と二人きりでいるのである。少しずつ、冷たくなった心が温まり始めていた。
二人で食事をしながら僕は正直に自分の思うところを吐露した。気が付いたら「撮影会ではモデルさんが絶対的に高貴なポジションの存在で、下々の僕ら(カメラマン)は接触の許されぬ存在だと思っていた。だから今こうして二人きりで食事をしていることが未だに信じられない。天から下々のところに下りてきたとかそういう感覚。というか下りてきていいの?」みたいなことを話していたのだ。共通の話題があり向こうも好意的だったお陰か、初めて可愛い女の子と二人きりになったわりには話は弾んで数時間はお喋りしていた。当時のレシートは今も記念に取ってある。
彼女の存在は僕に多大なる影響を与えた。個人的な撮影を頼まれただけとはいえ、僕にとっては生まれて初めて女の子から必要とされた瞬間だったのである。それまで僕のことを誰かに認めて欲しくて、承認を渇望し、女の子との関係性に飢えていた。自分が役に立たない、ダメ人間、死んだ方がマシ、でも仕方ないよね貴重な思春期を無駄に過ごしたのだから、と絶望を受け入れ静かに人生の敗戦処理をしていた。その荒んだ心の穴を埋めるように可愛い女の子から役割を与えられ、役に立つことが出来て、そして評価されたのである。
僕はそこで初めて僕を認めてもらえた、肯定してもらえたと思えるようになった。死にたい気持ちを押し殺すように、ずっと冷めた心を持ち続けていた僕は「この世で生きていてもいいよ」と彼女から生きることを許された気がしたのである。
極端に見えるかも知れない。しかし、可愛い女の子から何かを頼まれる、頼られるということは、言い方を変えれば彼女から何かを要求・期待されているわけであり、その要求・期待の裏には「死ぬことは許さん、生きてそれをやれ」が含まれているのである。振り返ってみれば、それまで異性から何かを依頼されたり期待されたりするような社会との関わり方をしたことが無かった。
もちろん僕の勝手な解釈だが、彼女からの「死ぬことは許さん、生きてそれをやれ」のメッセージがとても嬉しかった。彼女はきっと知らないだろうが僕にとっては命の恩人なのだ。キモイと思われようが、身分違いだろうが、僕は彼女のことを好きになっていた。
□モテない僕と可愛い女の子とのチグハグな関係
それから彼女と会う機会が一気に増えた。正確には彼女の追っかけになった。僕は彼女の出演する撮影会にはほぼ全て参加し、同伴して衣装などの荷物持ちになったり、アフターも一緒にゴハンをするようになったのである。彼女から個人撮影を頼まれたりもしたし、逆に僕の撮影練習にも付き合ってくれた。
撮影の前日はよく衣装の相談やリクエストを受けたりもした。畏れ多いことに僕がリクエストを出すと彼女は可能な限り応じてくれたのだ。ピンクのカーディガンはあたしのイメージと違うと言いつつ、恥じらいながらも撮らせてくれた。
気が付けば撮影会鉄の掟もどこへやら。あまり大っぴらには出来なかったが、メールや電話のやり取りなどは毎日していたし、毎週何らかのかたちで顔を合わせていたのである。撮影だけでなく衣装の買い物にも付き合ったり、二人でライブを見に行ったりもしていた。僕自身ここまで積極的に可愛い女の子と二人で一緒に行動するようになるとは思わなかったのだ。少し前まで絶望に支配されていたのがまるで嘘のようだった。
ただ一方で僕は二つの問題を抱えていた。一つは女の子の気持ちや考え方がどういう仕組みなのか、コミュニケーションスキルの無い僕にはさっぱり理解出来なかったこと。もう一つは僕が「彼女から生きる許可を貰った立場だ」という意識をどうしても捨てられなかったことである。仲が良かったことは確かだが、対等な関係ではいられなかった。
例えば僕はよく彼女を怒らせ、そして何故彼女が怒ったのかがわからなかった。彼女が遅刻する度に「モーニングコールしてって頼んだのに!」と怒られ、そうかこういうときは電話で起こすものなのかと思い、次に朝電話を掛けると「遅刻するから電話するな」と怒られた。僕はどうすればいいのか毎回苦悩することとなったのである。
またあるときは、友人から着信があり電話中だったのだが、同時に彼女も電話を掛けてきていたらしく「あたしが電話したときに別の人と電話中なんて有り得ない」という理由で怒られた。僕はどうしたらいいのか本当にわからず、しばらく怖くて彼女以外からの着信に出られなかった。
またあるときは、100円の買い物を「これ買ってよ」とせがまれたのだが、僕はそのやり取りが照れ臭くて「欲しかったら自分で買えばいいじゃん」と言ってしまい、その日一日口を聞いてくれなくなった。しかもそのとき僕はしばらく時間が経ってから「あれ?そういえば会話が止まった?」ということには気が付いたのだが、その時点でも何故彼女が不機嫌になったのかわからず、どうしようどうしようとオロオロしながらずっと会話の無い気まずい状態のまま一日を過ごし、夜になってから「まさか…アレが原因?」とようやく思い至る始末。そのことを謝罪してから彼女がようやく深い深いため息を吐いて、説教が始まった。責めを受けながらも僕は彼女が口を開いてくれたことに安堵した。
またあるときは、よく彼女の車で遠征撮影に行った。僕は運転免許を持っていなかったので、いつも助手席に乗っていたのだ。あるとき山中の奥深くまで行った際に彼女が虫に刺されてしまったのだが、僕は何気なく「ああ僕は虫になりたい」と呟いてしまい、彼女に本気でキモがられた。遠征時に失礼な発言で怒らせた場合、もし彼女が車に乗せてくれなかったら、僕には帰る手段がない。彼女の汚いモノを見るような視線に「僕はここに置いていかれるのではないか」とただ無防備に戦慄したのだった。
余談だが、人は何故挨拶をするかご存知だろうか? 人と会ったときに「こんにちは」の挨拶があることで「私はあなたの敵ではないですよ」を相手に伝えることが出来るのである。敵意がないのをお互い確認することで、安心して相手に心を開けるのだ。逆に知り合いなのに挨拶がなかったり、あるいは片方が無視したりすると、とたんにピリピリした空気が走る。
会話も同様で、片方が不意に口を閉ざしたりすると、急に空気が重くなる。特に二人っきりの車の中だったりするとそのピリピリの痛さは凄まじい。だが帰るために僕は、その針のムシロのような彼女の車に乗せてもらうしかなかった。僕は無口になった彼女がこの世で一番怖かったのである。
撮影の前日はよく衣装の相談やリクエストを受けたりもした。畏れ多いことに僕がリクエストを出すと彼女は可能な限り応じてくれたのだ。ピンクのカーディガンはあたしのイメージと違うと言いつつ、恥じらいながらも撮らせてくれた。
気が付けば撮影会鉄の掟もどこへやら。あまり大っぴらには出来なかったが、メールや電話のやり取りなどは毎日していたし、毎週何らかのかたちで顔を合わせていたのである。撮影だけでなく衣装の買い物にも付き合ったり、二人でライブを見に行ったりもしていた。僕自身ここまで積極的に可愛い女の子と二人で一緒に行動するようになるとは思わなかったのだ。少し前まで絶望に支配されていたのがまるで嘘のようだった。
ただ一方で僕は二つの問題を抱えていた。一つは女の子の気持ちや考え方がどういう仕組みなのか、コミュニケーションスキルの無い僕にはさっぱり理解出来なかったこと。もう一つは僕が「彼女から生きる許可を貰った立場だ」という意識をどうしても捨てられなかったことである。仲が良かったことは確かだが、対等な関係ではいられなかった。
例えば僕はよく彼女を怒らせ、そして何故彼女が怒ったのかがわからなかった。彼女が遅刻する度に「モーニングコールしてって頼んだのに!」と怒られ、そうかこういうときは電話で起こすものなのかと思い、次に朝電話を掛けると「遅刻するから電話するな」と怒られた。僕はどうすればいいのか毎回苦悩することとなったのである。
またあるときは、友人から着信があり電話中だったのだが、同時に彼女も電話を掛けてきていたらしく「あたしが電話したときに別の人と電話中なんて有り得ない」という理由で怒られた。僕はどうしたらいいのか本当にわからず、しばらく怖くて彼女以外からの着信に出られなかった。
またあるときは、100円の買い物を「これ買ってよ」とせがまれたのだが、僕はそのやり取りが照れ臭くて「欲しかったら自分で買えばいいじゃん」と言ってしまい、その日一日口を聞いてくれなくなった。しかもそのとき僕はしばらく時間が経ってから「あれ?そういえば会話が止まった?」ということには気が付いたのだが、その時点でも何故彼女が不機嫌になったのかわからず、どうしようどうしようとオロオロしながらずっと会話の無い気まずい状態のまま一日を過ごし、夜になってから「まさか…アレが原因?」とようやく思い至る始末。そのことを謝罪してから彼女がようやく深い深いため息を吐いて、説教が始まった。責めを受けながらも僕は彼女が口を開いてくれたことに安堵した。
またあるときは、よく彼女の車で遠征撮影に行った。僕は運転免許を持っていなかったので、いつも助手席に乗っていたのだ。あるとき山中の奥深くまで行った際に彼女が虫に刺されてしまったのだが、僕は何気なく「ああ僕は虫になりたい」と呟いてしまい、彼女に本気でキモがられた。遠征時に失礼な発言で怒らせた場合、もし彼女が車に乗せてくれなかったら、僕には帰る手段がない。彼女の汚いモノを見るような視線に「僕はここに置いていかれるのではないか」とただ無防備に戦慄したのだった。
余談だが、人は何故挨拶をするかご存知だろうか? 人と会ったときに「こんにちは」の挨拶があることで「私はあなたの敵ではないですよ」を相手に伝えることが出来るのである。敵意がないのをお互い確認することで、安心して相手に心を開けるのだ。逆に知り合いなのに挨拶がなかったり、あるいは片方が無視したりすると、とたんにピリピリした空気が走る。
会話も同様で、片方が不意に口を閉ざしたりすると、急に空気が重くなる。特に二人っきりの車の中だったりするとそのピリピリの痛さは凄まじい。だが帰るために僕は、その針のムシロのような彼女の車に乗せてもらうしかなかった。僕は無口になった彼女がこの世で一番怖かったのである。
□可愛い女の子が親しくしてくれるだけで幸せだった
とはいえ、基本的に彼女は僕に特別親しく接してくれた。いや、実際は誰にでも同様に優しかったのかもしれないが、少なくとも僕は自分でそう感じていたのだ。それだけに彼女を不機嫌にさせたときは自責の念を強くした。僕が無神経だったことが原因のときはもちろん、理不尽だと思う理由で怒られたときも結局は僕がそういう状況を招いたのだとただひたすら猛省したのだった。とにかくどんなときでも彼女は一片も悪くなく、完全に僕に落ち度があるのだと考えていた。何故なら彼女は僕から見れば絶世の美女で高貴な存在であり、絶望の淵を彷徨っていた僕に「生きる希望」を与えてくれたのだから。
だが、一方で彼女はどこまでいっても理解の出来ない存在でもあった。前の日に怒られて、どん底までに沈んでいた僕が次の日に一生懸命に考えた謝罪の弁を伝えると彼女はケラケラと笑いながら「まだそんなこと気にしてるのー?」という反応だった。まるで「その日その瞬間の気分が全て」だと言うかのようだったのだが、僕は前日怒らせたことがチャラになったとはとても思えず、何かと埋め合わせというか、どうにかして彼女を喜ばせようと意識していた。
彼女が学校の教室で撮影してみたいと言ったとき、ホイ来たとばかりにそのような撮影スタジオを探し出し、自前で撮影会を主催した。ちなみにスタジオの運営会社の方と現地でお会いしたとき僕は「監督の方ですか?」と声を掛けられた。「はい?いえ、違いますけど…」「あ、では男優の方ですか?」そこで初めて僕が借りた撮影スタジオがそのような撮影をする場所であることを知った。しまった、アダルトビデオの撮影スタジオに彼女を連れていくなんてセクハラ以外の何者でも無いじゃないかと僕はガクブルしていたのだが、彼女はその話を聞いて爆笑していた。
またあるときは、これは彼女を喜ばせようと意識したわけではないのだが、撮影会の際に彼女に積極的に親しく接するカメラマンがおり、僕は隅っこで不貞腐れていたことがある。そのカメラマンからセクハラを受けているわけではなかったし、参加者の一人である僕がどうこう出来る立場でもなかったのだが、僕はただ面白くなかった。だが会って間も無い女の子とあんなに親しくお喋り出来るそのカメラマンのコミュニケーションスキルを羨ましくも思っていたのだ。僕は羨望と嫉妬の眼差しを二人に向けていた。それが彼女にはバレバレだったらしく、後で「何?嫉妬したの?w嫉妬したの?ww」と嬉しそうだった。
結局のところ、彼女の機嫌が僕の躁鬱を左右した。たとえどんなワガママを言われても彼女が上機嫌であれば僕も幸福感を抱き、たとえ理不尽な理由でも彼女が不機嫌になれば僕は自分を責めていた。
気が付けば僕と彼女は仲が良かったとはいえ、かなり歪な関係であった。彼女と一緒にいることが僕にとって天国であり地獄だったのである。客観的に見ても惚れた弱み、という範疇を遥かに超えていただろう。僕にとって彼女は「生きる理由」そのものであり、彼女がいることで僕は初めて自分の実存を感じることが出来た。だからいくら都合よく切り捨てられても、必要な度に呼び出されても、それでも好きな女の子に必要とされるなら、それは僕にとって喜ぶべきことだったのである。
だが、一方で彼女はどこまでいっても理解の出来ない存在でもあった。前の日に怒られて、どん底までに沈んでいた僕が次の日に一生懸命に考えた謝罪の弁を伝えると彼女はケラケラと笑いながら「まだそんなこと気にしてるのー?」という反応だった。まるで「その日その瞬間の気分が全て」だと言うかのようだったのだが、僕は前日怒らせたことがチャラになったとはとても思えず、何かと埋め合わせというか、どうにかして彼女を喜ばせようと意識していた。
彼女が学校の教室で撮影してみたいと言ったとき、ホイ来たとばかりにそのような撮影スタジオを探し出し、自前で撮影会を主催した。ちなみにスタジオの運営会社の方と現地でお会いしたとき僕は「監督の方ですか?」と声を掛けられた。「はい?いえ、違いますけど…」「あ、では男優の方ですか?」そこで初めて僕が借りた撮影スタジオがそのような撮影をする場所であることを知った。しまった、アダルトビデオの撮影スタジオに彼女を連れていくなんてセクハラ以外の何者でも無いじゃないかと僕はガクブルしていたのだが、彼女はその話を聞いて爆笑していた。
またあるときは、これは彼女を喜ばせようと意識したわけではないのだが、撮影会の際に彼女に積極的に親しく接するカメラマンがおり、僕は隅っこで不貞腐れていたことがある。そのカメラマンからセクハラを受けているわけではなかったし、参加者の一人である僕がどうこう出来る立場でもなかったのだが、僕はただ面白くなかった。だが会って間も無い女の子とあんなに親しくお喋り出来るそのカメラマンのコミュニケーションスキルを羨ましくも思っていたのだ。僕は羨望と嫉妬の眼差しを二人に向けていた。それが彼女にはバレバレだったらしく、後で「何?嫉妬したの?w嫉妬したの?ww」と嬉しそうだった。
結局のところ、彼女の機嫌が僕の躁鬱を左右した。たとえどんなワガママを言われても彼女が上機嫌であれば僕も幸福感を抱き、たとえ理不尽な理由でも彼女が不機嫌になれば僕は自分を責めていた。
気が付けば僕と彼女は仲が良かったとはいえ、かなり歪な関係であった。彼女と一緒にいることが僕にとって天国であり地獄だったのである。客観的に見ても惚れた弱み、という範疇を遥かに超えていただろう。僕にとって彼女は「生きる理由」そのものであり、彼女がいることで僕は初めて自分の実存を感じることが出来た。だからいくら都合よく切り捨てられても、必要な度に呼び出されても、それでも好きな女の子に必要とされるなら、それは僕にとって喜ぶべきことだったのである。
■Chapter.3 僕は、いつだって、馬鹿で、身勝手だった
□次第に「与えてくれること」を相手に求めるようになった
小中学生の頃の多少のやんちゃを除けば、僕は今まで一度だって人に暴力を振るったことはなかった。友達とケンカをしたときも相手に怪我を負わせるようなことは無かったし、まして女性に手を上げるなんて行為は僕が一番忌み嫌うことだった。相手を暴力で支配することは最低だと思っていたし、人は言葉を通して出来るだけ理解し合うべきだと思っていたのだ。
僕は小さい頃からケンカをすると必ず負ける立場だった。だから対決するときはいつも直接の殴り合いにならないよう注意しつつ、でも相手の立場が悪くなるような策を練った。平たく言うと、学校の先生やギャラリーを味方に付けたのだ。ただ直接先生に告げ口をすると、結局後でいじめっ子から報復を受けてしまう。直接犯人にならないように僕はいつも「周囲に状況を察してもらい、自発的に介入してもらう」という術を採った。それが僕の生存戦略だったのだ。
大人になると僕は暴力や暴言に頼らない人間となった代わりに、遠回しに自分の欲求を察してもらう人間となった。何かをお願いしたいときには直接それを相手に言うのではなく、相手が自発的に申し出てくれるような状況を作ろうとするのだ。僕は相手にどれだけ文句や不満があっても決して怒らなかったが、その代わり皮肉や自虐が口を突いて出ていた。そうすることで相手が自発的に謝罪することをやはり僕は期待していたのだ。
僕は彼女から必要とされること、認められることで「生きている実感」を与えられていた。いつも与えられていたから、与えられていることに鈍感になっていたのだ。少しでも彼女からの承認が不足すると、それが僕自身に原因があるとは微塵も思わずに、無条件で補充されることを望み、彼女に察してもらうのを待っていた。その与えられる関係性を維持したいという方向に「彼女のために」ではなく「僕自身のために」構ってくれることを望んだのだ。
僕はご褒美が欲しかった。僕を認めて欲しかった。それがただの依存であることなど気付かず、彼女がいつも与えてくれるのを当然のことのように、いつの間にか僕は勘違いをして、ワガママになっていた。
よくイベント等で二人きりで撮影しているカメラ小僧とコスプレイヤーがいるだろう。そのコスプレイヤーがとても可愛い女の子で、他のカメラ小僧が「こちらも撮影をお願いしていいですか?」と声を掛けても「撮影は彼に頼んでいるので、他の方はごめんなさい」と断られるパターンだ。
実のところ、僕はよくこのようなパターンで撮影を頼まれていた。僕だけ優遇された気分で鼻高々になっていたのである。
だが、僕も大学の卒業を控えて次第に忙しくなると、今までのようにいつも彼女の追っかけをするというわけにはいかなくなった。彼女はもちろん通常通り撮影会などで他のカメラマンとも顔を合わせていただろうし、個人撮影などがあれば応じていただろう。だがその写真がブログなどに載っているのを見ると、僕は羨望と嫉妬の感情を抱き、隠さなくなっていたのだ。僕は自分が優遇されていないように感じ、みっともなく逆ギレしていた。
「キレた」といっても前述の通り怒鳴ったり暴力を振るったりした訳ではない。久しぶりに彼女と顔を合わせたときに、さりげなく嫉妬の滲み出た自虐を呟いていたのだ。以前僕が嫉妬したときに彼女が喜んでくれた記憶を頼りに、こうすれば好意的に察してくれるだろうということを自己中心的に繰り返していた。
また撮影自体にも僕のワガママが出るようになっていた。彼女がこういう撮影をしたい。こういう写真が欲しいという希望を僕は聞き流し、僕は僕が撮りたいように撮影を企画し、それを彼女に無理矢理頼んでいたのだ。大分棘のある言葉でメールのやり取りをしてしまっていたが、それでも僕はあくまで彼女から「与えられている立場」であり、彼女の機嫌が全てであることには変わりはなかった。だから彼女から不機嫌な言葉が返ってきたときはいつも通りオロオロしていた。そして僕が落ち込んだり、困惑したり、戦慄したりするのは彼女からの棘のあるメールが原因だと思い込んでいたのだ。僕は悪くない、彼女には僕の殺傷与奪の権限があるのだから、と僕はその関係性にいつの間にか酔っていた。
彼女は僕が彼女に構って欲しいと思っていることを知っていたし、だから会う度に僕を困らせて楽しんでいた。周囲から見れば飼い主と下僕というロールプレイのように見えただろう。だが実際は逆であり、僕が彼女に僕を困らせるようにワガママな要求をし続けていた。しかも始末に負えなかったのは、僕自身そのことに気付かないまま彼女を支配しようとしていたことだ。
きごちないながらも、奇妙にバランスの取れていた僕と彼女の関係は、少しずつ、でも確実におかしくなっていった。徐々にお互いの信頼感がすれ違い、微妙な空気になっていたことにおかしいなと思いつつ、それでもこの状態に満足し、酔っていた僕は何も見ないフリをし続けていたのだ。
そしてそのような状態が続いた結果、彼女の方が完全に参ってしまった。彼女にとって僕は「頼れるカメラマン」から「ただの重荷」になっていたのだ。それはそうだろう。暴力的ではないにせよ、会う度に自虐や皮肉をグチグチ繰り返す男なのだ。一緒にいて楽しくなければ、何の為に時間を割いて顔を合わせているのかわからなかったに違いなかった。
ある日、彼女にしては珍しく長文のメールを送ってきた。いつも一言二言お喋り口調だったはずのメールは、やけに丁寧なですます調の文章だった。僕たちは付き合っていたのかといえばそうではなく、どちらかというとチグハグで歪な関係だった。だから別れ話のメールではない。そこには淡々と彼女の今の感情が綴ってあった。
少しずつ僕に対して悪印象を溜めていたのだろう。それがある日許容度を超えて溢れてしまった。その瞬間、彼女は僕に興味を失ったのだ。それを僕に伝える内容だった。
僕は小さい頃からケンカをすると必ず負ける立場だった。だから対決するときはいつも直接の殴り合いにならないよう注意しつつ、でも相手の立場が悪くなるような策を練った。平たく言うと、学校の先生やギャラリーを味方に付けたのだ。ただ直接先生に告げ口をすると、結局後でいじめっ子から報復を受けてしまう。直接犯人にならないように僕はいつも「周囲に状況を察してもらい、自発的に介入してもらう」という術を採った。それが僕の生存戦略だったのだ。
大人になると僕は暴力や暴言に頼らない人間となった代わりに、遠回しに自分の欲求を察してもらう人間となった。何かをお願いしたいときには直接それを相手に言うのではなく、相手が自発的に申し出てくれるような状況を作ろうとするのだ。僕は相手にどれだけ文句や不満があっても決して怒らなかったが、その代わり皮肉や自虐が口を突いて出ていた。そうすることで相手が自発的に謝罪することをやはり僕は期待していたのだ。
僕は彼女から必要とされること、認められることで「生きている実感」を与えられていた。いつも与えられていたから、与えられていることに鈍感になっていたのだ。少しでも彼女からの承認が不足すると、それが僕自身に原因があるとは微塵も思わずに、無条件で補充されることを望み、彼女に察してもらうのを待っていた。その与えられる関係性を維持したいという方向に「彼女のために」ではなく「僕自身のために」構ってくれることを望んだのだ。
僕はご褒美が欲しかった。僕を認めて欲しかった。それがただの依存であることなど気付かず、彼女がいつも与えてくれるのを当然のことのように、いつの間にか僕は勘違いをして、ワガママになっていた。
よくイベント等で二人きりで撮影しているカメラ小僧とコスプレイヤーがいるだろう。そのコスプレイヤーがとても可愛い女の子で、他のカメラ小僧が「こちらも撮影をお願いしていいですか?」と声を掛けても「撮影は彼に頼んでいるので、他の方はごめんなさい」と断られるパターンだ。
実のところ、僕はよくこのようなパターンで撮影を頼まれていた。僕だけ優遇された気分で鼻高々になっていたのである。
だが、僕も大学の卒業を控えて次第に忙しくなると、今までのようにいつも彼女の追っかけをするというわけにはいかなくなった。彼女はもちろん通常通り撮影会などで他のカメラマンとも顔を合わせていただろうし、個人撮影などがあれば応じていただろう。だがその写真がブログなどに載っているのを見ると、僕は羨望と嫉妬の感情を抱き、隠さなくなっていたのだ。僕は自分が優遇されていないように感じ、みっともなく逆ギレしていた。
「キレた」といっても前述の通り怒鳴ったり暴力を振るったりした訳ではない。久しぶりに彼女と顔を合わせたときに、さりげなく嫉妬の滲み出た自虐を呟いていたのだ。以前僕が嫉妬したときに彼女が喜んでくれた記憶を頼りに、こうすれば好意的に察してくれるだろうということを自己中心的に繰り返していた。
また撮影自体にも僕のワガママが出るようになっていた。彼女がこういう撮影をしたい。こういう写真が欲しいという希望を僕は聞き流し、僕は僕が撮りたいように撮影を企画し、それを彼女に無理矢理頼んでいたのだ。大分棘のある言葉でメールのやり取りをしてしまっていたが、それでも僕はあくまで彼女から「与えられている立場」であり、彼女の機嫌が全てであることには変わりはなかった。だから彼女から不機嫌な言葉が返ってきたときはいつも通りオロオロしていた。そして僕が落ち込んだり、困惑したり、戦慄したりするのは彼女からの棘のあるメールが原因だと思い込んでいたのだ。僕は悪くない、彼女には僕の殺傷与奪の権限があるのだから、と僕はその関係性にいつの間にか酔っていた。
彼女は僕が彼女に構って欲しいと思っていることを知っていたし、だから会う度に僕を困らせて楽しんでいた。周囲から見れば飼い主と下僕というロールプレイのように見えただろう。だが実際は逆であり、僕が彼女に僕を困らせるようにワガママな要求をし続けていた。しかも始末に負えなかったのは、僕自身そのことに気付かないまま彼女を支配しようとしていたことだ。
きごちないながらも、奇妙にバランスの取れていた僕と彼女の関係は、少しずつ、でも確実におかしくなっていった。徐々にお互いの信頼感がすれ違い、微妙な空気になっていたことにおかしいなと思いつつ、それでもこの状態に満足し、酔っていた僕は何も見ないフリをし続けていたのだ。
そしてそのような状態が続いた結果、彼女の方が完全に参ってしまった。彼女にとって僕は「頼れるカメラマン」から「ただの重荷」になっていたのだ。それはそうだろう。暴力的ではないにせよ、会う度に自虐や皮肉をグチグチ繰り返す男なのだ。一緒にいて楽しくなければ、何の為に時間を割いて顔を合わせているのかわからなかったに違いなかった。
ある日、彼女にしては珍しく長文のメールを送ってきた。いつも一言二言お喋り口調だったはずのメールは、やけに丁寧なですます調の文章だった。僕たちは付き合っていたのかといえばそうではなく、どちらかというとチグハグで歪な関係だった。だから別れ話のメールではない。そこには淡々と彼女の今の感情が綴ってあった。
少しずつ僕に対して悪印象を溜めていたのだろう。それがある日許容度を超えて溢れてしまった。その瞬間、彼女は僕に興味を失ったのだ。それを僕に伝える内容だった。
□首輪を外されても、飼い主のそばを離れられない
もう会わないようにしましょう、というメールに僕は了承の返信をした。不思議と感情が爆発したりはしなかった。いや、落ち着いていたのはもうとっくにこの関係性が崩壊していて、その確認だったからだ。僕は心のどこかでなんとなくこうなる予感がしていた。
僕自身嫉妬していたことを自覚していたし、それでもこの一方的な関係に満足してしまっていた。もともとは彼女が僕の撮影を認め、評価してくれたことに僕は喜びを見出していた筈が、いつの間にか彼女と一緒にいて彼女を撮って楽しければそれでいいという状態になっていたのだ。このままでは自分がどんどんダメになるとも薄々感じていた。そして彼女も「あたしが近くにいると相手をさらにダメにしてしまう」と感じていたのだろう。僕は幸せのあまり後先のことなど考えず、このままダメになってしまってもいいと考えていたのだ。そして来るべくしてその日が来てしまった。ただそれだけなのだ。だから彼女のメールの文章が不思議なほどにすんなり僕の頭に入ってきて、自然に納得出来てしまった。
だが、気持ちの整理が着いていた訳でも、自然消滅で最初から感情がニュートラルだった訳でもなかった。「彼女のことを忘れてしまうには、僕にとって勿体ないくらいあまりに素敵な女性過ぎるんだ」「どうせそれ本人に伝えてなかったんだろ」この話を聞いてもらっていた友達がいたのだが、その友達は僕のパソコンの付近に飾ってある彼女の写った写真を手に取って「さぁ決別だ、今ここでパンチをしろ」と言ってきた。結論から言えば出来なかった。彼女を嫌いになったわけではなかったし、僕が今まで撮った彼女の写真を破いたり捨てたり焼いたりはどうしても出来なかったのだ。全身から血が流れ出る感覚になるのである。痛い。
決して綺麗な終わり方ではないし、僕はやはりどこかドロドロしていた。「あのときああしていればよかった」みたいな後悔があっても、きっとそのときの僕のキャパシティから考えて絶対に出来なかった。もともとコミュニケーションスキルの経験値がない男だ。だから「ああしていればよかった」という後悔はすぐに「でも、ああすることしか出来なかった」という諦めに置き換わった。
諦めはあるけれど、こうなってから初めて色んなものが一気に見えてきて、如何に僕が何も見えていなかったかを思い知らされたのだ。今考えてみれば彼女から色んなサインがあった。彼女から同じことを繰り返し言われていたのだ。そのとき僕は何を言っているのかがわからなかった。あるいはサインをサインとして認識していなかった。彼女が何を言いたかったのか、僕に何をして欲しかったのか、今になってからようやく全部わかったのである。
皮肉な話である。この点はとても悔しい。出会った頃は彼女のサインを読み取ろうと必死だったのに、僕はこんなにも彼女に対して怠けていたなんて。関係が終わってから気付くなんて。あああああ。
…と、まぁ最初僕は感傷に浸り心の整理を着けようという方向に意識が向いていたのだが、すぐに耐えられなくなった。彼女の存在があって僕が存在出来る、という心理状態だったのだから当然とも言える。ここから先は泥沼の展開が待っていたのだ。
基本的にその長文メールを境にメールや電話のやり取りはもちろん、顔を合わせることも全てパタリと止んだ。「会わないようにしましょう」「わかりました」のやり取りをしたのだから当然なのだが、時間が経つにつれ彼女への諦めきれない想いを募らせるだけであった。
彼女とは会っていなかったが、僕や彼女と共通の友達のモデルさんやカメラマンさんとはよく会っており、打ち上げの際は「君たちいつも一緒にいたのに何があったの?」と根掘り葉掘り聞かれたりもした。正直に「全部僕が悪いんです」と懺悔の弁を述べていると「女の子はね、いつもそのときそのときの感情で話しているから、そのときは本気のつもりで話していても、多分本気で本気なわけじゃないんだよ」「何?本当に会わないつもりなの?試されてるんだよー」「あたしは数ヵ月後きっと普通に彼女の隣に君がいると思うけど」というように、面白半分相談半分に酒の肴にされていた。
彼女に会えば僕はまた依存を強くしてダメになるということは分かり切っていた。この決別はきっと人生でプラスになる。だからもう彼女とは会わないようにしようと固く決心していた。だが早くも僕の心は折れかけていて、結局は酒の席での甘い言葉に希望を言い出してしまったのである。「彼女が何を言いたかったのか、僕に何をして欲しかったのか、今となってからは全部わかる」と反省していたのは最初のほんの一瞬だけで、僕はすぐに元の傲慢な僕に戻っていた。ただひたすら「また僕のことを認めて欲しい」という欲求に囚われ、何も見えなくなっていたのである。
気が付いたら彼女の誕生日に、彼女のオフ会に申し込んでいた。会ってどうこうしようという訳ではなく、ただ彼女の顔が見たくて、彼女の声が聞きたかったのである。とはいえ彼女の会いたくないという意思を無視した訳であり、僕はただのストーカーに成り下がっていた。
僕は自分勝手に、彼女の誕生日のオフ会だから何かプレゼントを持っていったら喜ばれるだろうと考えていた。過去にどういう系統のものをプレゼントしていたかを思い出しながら街を散策し、そういえば以前コスプレ衣装を丸々一式プレゼントしたら彼女に喜ばれたっけと思い至った。僕は自身の置かれた立場を何も考えず、何も見えていなかった。僕は彼女の立場でものを考えずに、再び同じ過ちを犯したのだ。僕はただ単に「僕が彼女に着せて撮りたい衣装」を購入してオフ会に持って行った。分かりやすく書くと、彼女にアダルトな水着を渡した。僕の人生で最大級の愚行だった。
彼女がオフ会のその場で包みを開けなかった為、僕自身に直接雷は落ちなかった。だが時間が経過するにつれて、共通の友人たちの空気が強烈に冷たくなっていたことに気付いた。僕は本当に本当にどこまでも大馬鹿で身勝手だったのだ。
僕自身嫉妬していたことを自覚していたし、それでもこの一方的な関係に満足してしまっていた。もともとは彼女が僕の撮影を認め、評価してくれたことに僕は喜びを見出していた筈が、いつの間にか彼女と一緒にいて彼女を撮って楽しければそれでいいという状態になっていたのだ。このままでは自分がどんどんダメになるとも薄々感じていた。そして彼女も「あたしが近くにいると相手をさらにダメにしてしまう」と感じていたのだろう。僕は幸せのあまり後先のことなど考えず、このままダメになってしまってもいいと考えていたのだ。そして来るべくしてその日が来てしまった。ただそれだけなのだ。だから彼女のメールの文章が不思議なほどにすんなり僕の頭に入ってきて、自然に納得出来てしまった。
だが、気持ちの整理が着いていた訳でも、自然消滅で最初から感情がニュートラルだった訳でもなかった。「彼女のことを忘れてしまうには、僕にとって勿体ないくらいあまりに素敵な女性過ぎるんだ」「どうせそれ本人に伝えてなかったんだろ」この話を聞いてもらっていた友達がいたのだが、その友達は僕のパソコンの付近に飾ってある彼女の写った写真を手に取って「さぁ決別だ、今ここでパンチをしろ」と言ってきた。結論から言えば出来なかった。彼女を嫌いになったわけではなかったし、僕が今まで撮った彼女の写真を破いたり捨てたり焼いたりはどうしても出来なかったのだ。全身から血が流れ出る感覚になるのである。痛い。
決して綺麗な終わり方ではないし、僕はやはりどこかドロドロしていた。「あのときああしていればよかった」みたいな後悔があっても、きっとそのときの僕のキャパシティから考えて絶対に出来なかった。もともとコミュニケーションスキルの経験値がない男だ。だから「ああしていればよかった」という後悔はすぐに「でも、ああすることしか出来なかった」という諦めに置き換わった。
諦めはあるけれど、こうなってから初めて色んなものが一気に見えてきて、如何に僕が何も見えていなかったかを思い知らされたのだ。今考えてみれば彼女から色んなサインがあった。彼女から同じことを繰り返し言われていたのだ。そのとき僕は何を言っているのかがわからなかった。あるいはサインをサインとして認識していなかった。彼女が何を言いたかったのか、僕に何をして欲しかったのか、今になってからようやく全部わかったのである。
皮肉な話である。この点はとても悔しい。出会った頃は彼女のサインを読み取ろうと必死だったのに、僕はこんなにも彼女に対して怠けていたなんて。関係が終わってから気付くなんて。あああああ。
…と、まぁ最初僕は感傷に浸り心の整理を着けようという方向に意識が向いていたのだが、すぐに耐えられなくなった。彼女の存在があって僕が存在出来る、という心理状態だったのだから当然とも言える。ここから先は泥沼の展開が待っていたのだ。
基本的にその長文メールを境にメールや電話のやり取りはもちろん、顔を合わせることも全てパタリと止んだ。「会わないようにしましょう」「わかりました」のやり取りをしたのだから当然なのだが、時間が経つにつれ彼女への諦めきれない想いを募らせるだけであった。
彼女とは会っていなかったが、僕や彼女と共通の友達のモデルさんやカメラマンさんとはよく会っており、打ち上げの際は「君たちいつも一緒にいたのに何があったの?」と根掘り葉掘り聞かれたりもした。正直に「全部僕が悪いんです」と懺悔の弁を述べていると「女の子はね、いつもそのときそのときの感情で話しているから、そのときは本気のつもりで話していても、多分本気で本気なわけじゃないんだよ」「何?本当に会わないつもりなの?試されてるんだよー」「あたしは数ヵ月後きっと普通に彼女の隣に君がいると思うけど」というように、面白半分相談半分に酒の肴にされていた。
彼女に会えば僕はまた依存を強くしてダメになるということは分かり切っていた。この決別はきっと人生でプラスになる。だからもう彼女とは会わないようにしようと固く決心していた。だが早くも僕の心は折れかけていて、結局は酒の席での甘い言葉に希望を言い出してしまったのである。「彼女が何を言いたかったのか、僕に何をして欲しかったのか、今となってからは全部わかる」と反省していたのは最初のほんの一瞬だけで、僕はすぐに元の傲慢な僕に戻っていた。ただひたすら「また僕のことを認めて欲しい」という欲求に囚われ、何も見えなくなっていたのである。
気が付いたら彼女の誕生日に、彼女のオフ会に申し込んでいた。会ってどうこうしようという訳ではなく、ただ彼女の顔が見たくて、彼女の声が聞きたかったのである。とはいえ彼女の会いたくないという意思を無視した訳であり、僕はただのストーカーに成り下がっていた。
僕は自分勝手に、彼女の誕生日のオフ会だから何かプレゼントを持っていったら喜ばれるだろうと考えていた。過去にどういう系統のものをプレゼントしていたかを思い出しながら街を散策し、そういえば以前コスプレ衣装を丸々一式プレゼントしたら彼女に喜ばれたっけと思い至った。僕は自身の置かれた立場を何も考えず、何も見えていなかった。僕は彼女の立場でものを考えずに、再び同じ過ちを犯したのだ。僕はただ単に「僕が彼女に着せて撮りたい衣装」を購入してオフ会に持って行った。分かりやすく書くと、彼女にアダルトな水着を渡した。僕の人生で最大級の愚行だった。
彼女がオフ会のその場で包みを開けなかった為、僕自身に直接雷は落ちなかった。だが時間が経過するにつれて、共通の友人たちの空気が強烈に冷たくなっていたことに気付いた。僕は本当に本当にどこまでも大馬鹿で身勝手だったのだ。
□気が付けば鬱になっていた
結局のところ、僕は最初から最後まで自分の自尊心のことしか見ていなかったし、考えていなかったのである。僕が恥ずかしい思いをしないこと、僕が傷付かないこと、僕が落ち込まないこと、それがが僕の中では一番大事なことだった。
例えば僕に好きな女の子がいて相手に想いを伝えたくても、告白するからには絶対に失敗するわけにはいかない、100%成功しなければならないと考えてしまっていた。相手にフラれてしまったら僕の心が傷付く、そして「あいつ女の子にフラれたんだぜ」と周囲に言われて僕が恥ずかしい思いをする、そんなことは絶対に回避しなければならなかった。僕にとって失敗することは死ぬことと同義だったから、死ぬことが怖くて僕は一度も勝負することが出来なかったのだ。自分が一番可愛い、自分の自尊心が一番大事、という生き方しか知らなかった僕は、大人になってからもずっと世界一の意気地無しであり続けたのだ。
だから僕の中では「人格を持っている他者の存在」が原理的に理解出来ていなかったし、きっと今も理解出来ていないのだ。言葉でいくら「相手の視点に立ち、相手の気持ちを考える」といっても、結局相手のことなど考えることが出来ず、僕は僕が喜ぶことしかしないという実に都合の良い人間だった。
僕は好きだった相手をいつも傷付けてしまう最低最悪の人間だったのだ。それがどうしても許せなかった。気持ちがグチャグチャに潰れ、仕事でもヘマを連発するようになり、何もかもが手に付かなくなった。
そのうち何も考えられなくなり、それでも仕事のある身で引き篭るわけにもいかず、再び心療内科に通うようになった。彼女を傷付けながら、周囲に迷惑を撒き散らしながら、僕は僕自身のことをかわいそうな悲劇のヒロインとして演じていた。そうすることで誰かにヨシヨシと慰めてもらいたかったのだ。どこまでも身勝手だった。そしてそれを自覚出来る程度には冷静で、どんどん自己嫌悪に陥っていった。
結局通院での小康状態にも破綻を迎え、朝どうしてもベッドから起きられなくなった。ゴハンも砂の味しかせず、過敏性胃腸炎による血便も止まらなくなった。もはや彼女の存在がどうこうということより、自己嫌悪と自己否定の底無し沼で溺死しかけていたのである。今度こそ本物の鬱病だった。自力での改善が困難だと悟り、職場との相談の上で休職と入院を決意したのだった。
年末に休職を決め、入院は年明けからであった。心配していた友達から「こういうときこそ遊びに行かなきゃ」と冬コミに誘われ、僕は少し迷ったが新刊の誘惑につられて有明に赴いた。
絶望をなんとか受け流しながらも、最初の諦観の気持ちを思い出していた。「恋愛は諦める」「人生に期待するな」そもそもこれは僕の緊急避難的な決心だった。次に考えていたのは「人生に意味なんか無い」である。僕が生きる意味は──なんて難しいことを考えるから精神を病むのだ。高尚な悩みには思いっきり低俗なことをすべきである。だから大晦日の今こうして偽MIDI泥の会の最後尾に並んでいるのだ。一通り買い物が終わったら、コスプレ広場で写真も撮りまくろう。高校時代からオタクとして通い続けていたコミケは、僕にとって自由な雰囲気で、何でもありで、猥雑で、そしていつも変わらずそこにあった。それがこのような精神状態の時は特に心に沁み、癒しの効果があったのだ。もちろん僕が勝手にそう解釈しただけなのだが。
最後に、僕を有明に連れてきた友人がちょっとした計らいをしてくれた。なんと彼女が会場に来ており、入院前の僕と会わせてくれたのだ。完全に嫌われたと思っていた僕だったが、彼女は人づてに僕の状況を聞いており心配していたのだという。もちろん元の関係には戻らないだろうが、彼女は穏やかな表情をしていた。入院することを告げると、あの件はもう気にしてないから、元気になるようにと頭を撫でられた。最後の命令だった。
例えば僕に好きな女の子がいて相手に想いを伝えたくても、告白するからには絶対に失敗するわけにはいかない、100%成功しなければならないと考えてしまっていた。相手にフラれてしまったら僕の心が傷付く、そして「あいつ女の子にフラれたんだぜ」と周囲に言われて僕が恥ずかしい思いをする、そんなことは絶対に回避しなければならなかった。僕にとって失敗することは死ぬことと同義だったから、死ぬことが怖くて僕は一度も勝負することが出来なかったのだ。自分が一番可愛い、自分の自尊心が一番大事、という生き方しか知らなかった僕は、大人になってからもずっと世界一の意気地無しであり続けたのだ。
だから僕の中では「人格を持っている他者の存在」が原理的に理解出来ていなかったし、きっと今も理解出来ていないのだ。言葉でいくら「相手の視点に立ち、相手の気持ちを考える」といっても、結局相手のことなど考えることが出来ず、僕は僕が喜ぶことしかしないという実に都合の良い人間だった。
僕は好きだった相手をいつも傷付けてしまう最低最悪の人間だったのだ。それがどうしても許せなかった。気持ちがグチャグチャに潰れ、仕事でもヘマを連発するようになり、何もかもが手に付かなくなった。
そのうち何も考えられなくなり、それでも仕事のある身で引き篭るわけにもいかず、再び心療内科に通うようになった。彼女を傷付けながら、周囲に迷惑を撒き散らしながら、僕は僕自身のことをかわいそうな悲劇のヒロインとして演じていた。そうすることで誰かにヨシヨシと慰めてもらいたかったのだ。どこまでも身勝手だった。そしてそれを自覚出来る程度には冷静で、どんどん自己嫌悪に陥っていった。
結局通院での小康状態にも破綻を迎え、朝どうしてもベッドから起きられなくなった。ゴハンも砂の味しかせず、過敏性胃腸炎による血便も止まらなくなった。もはや彼女の存在がどうこうということより、自己嫌悪と自己否定の底無し沼で溺死しかけていたのである。今度こそ本物の鬱病だった。自力での改善が困難だと悟り、職場との相談の上で休職と入院を決意したのだった。
年末に休職を決め、入院は年明けからであった。心配していた友達から「こういうときこそ遊びに行かなきゃ」と冬コミに誘われ、僕は少し迷ったが新刊の誘惑につられて有明に赴いた。
絶望をなんとか受け流しながらも、最初の諦観の気持ちを思い出していた。「恋愛は諦める」「人生に期待するな」そもそもこれは僕の緊急避難的な決心だった。次に考えていたのは「人生に意味なんか無い」である。僕が生きる意味は──なんて難しいことを考えるから精神を病むのだ。高尚な悩みには思いっきり低俗なことをすべきである。だから大晦日の今こうして偽MIDI泥の会の最後尾に並んでいるのだ。一通り買い物が終わったら、コスプレ広場で写真も撮りまくろう。高校時代からオタクとして通い続けていたコミケは、僕にとって自由な雰囲気で、何でもありで、猥雑で、そしていつも変わらずそこにあった。それがこのような精神状態の時は特に心に沁み、癒しの効果があったのだ。もちろん僕が勝手にそう解釈しただけなのだが。
最後に、僕を有明に連れてきた友人がちょっとした計らいをしてくれた。なんと彼女が会場に来ており、入院前の僕と会わせてくれたのだ。完全に嫌われたと思っていた僕だったが、彼女は人づてに僕の状況を聞いており心配していたのだという。もちろん元の関係には戻らないだろうが、彼女は穏やかな表情をしていた。入院することを告げると、あの件はもう気にしてないから、元気になるようにと頭を撫でられた。最後の命令だった。
■Chapter.4 そしてM属性だけが残った
□無視以外だったら、何をされてもきっと嬉しかった
それ以来彼女とは会っていない。完全に連絡先を断ってしまったので、どこで何をしているかを知る由もない。きっぱりと吹っ切ることにしたのだ。彼女のせいではまったくないが、僕は彼女といると自分をダメにする方に向いてしまう。人と出会い、親しくなったことは決して不幸なことではないが、ある意味では悲劇の組み合わせではあったかもしれない。
振り返ると、最初あのときどうして彼女は僕に親しくしてくれたのだろう? もしかしたら僕と同じだったのかもしれないと思うようになった。つまり、お互い誰かに自分のことを認めて欲しかったのである。誰かが認めてくれないと、自分が存在出来なかった。自分が何者なのかわからなったのだ。
要は双方自分のことが大事で「与えてくれること」を相手に求め続けていた。それが周囲から見て完全に飼い主と下僕という構図に見えたらしい。「君はただ利用されていただけだよ?悔しくないの?」と言われても、金品を貢いだわけではないし、頻繁に食事を奢らされたわけでもないし、車も運転出来なかったらアッシーでもなかったし、むしろ役目を与えられて、生きる居場所が出来て、嬉しかったのである。
僕は彼女が欲しいというよりも、女の子に存在を認められたかった。存在が成立する為には、女の子に僕という存在を一人の人格としてを認識してもらい、そしてそれが僕にわかるかたちで反応を返してもらうことだった。コミュニケーションが成立することが必要だったのだ。会話ややり取りが成立すれば、それが命令だろうが、弄びだろうが、踏みつけだろうが、痛めつけだろうが、僕という存在が相手の女の子の中で成立していることに変わりはなかったのである。
だから好意的なやり取りに越したことはないが、たとえ負のやり取りでも、それが無視や絶縁でなければ僕は構わなかったのだ。極端な話、女の子に怪我をさせられても、たとえ殺されても、相手が僕という人格を認識し、僕にわかるように反応を返してくれた、という証拠になるのならそれでもきっと嬉しかった。いや、本当は痛いのは嫌だけど。だが自己評価が低い状態のままだったら、僕が存在するにはこれしか方法がないのだと絶望しながら受け入れていたかも知れない。
恐らく理解出来ない人には意味がわからないだろう。そこまで女の子に認めて欲しいのなら自分で勇気を出してちゃんと相手を口説けよ、相手に想いを伝えろよ、と言うかもしれない。普通はそう考えるのだろう。上手く表現は出来ないが、小さい頃から失敗を避けながら脆弱に育ってしまい、打たれ弱いなかで生きている実感を得ようとすると、そういう歪んだ実存形式になってしまうのである。
振り返ると、最初あのときどうして彼女は僕に親しくしてくれたのだろう? もしかしたら僕と同じだったのかもしれないと思うようになった。つまり、お互い誰かに自分のことを認めて欲しかったのである。誰かが認めてくれないと、自分が存在出来なかった。自分が何者なのかわからなったのだ。
要は双方自分のことが大事で「与えてくれること」を相手に求め続けていた。それが周囲から見て完全に飼い主と下僕という構図に見えたらしい。「君はただ利用されていただけだよ?悔しくないの?」と言われても、金品を貢いだわけではないし、頻繁に食事を奢らされたわけでもないし、車も運転出来なかったらアッシーでもなかったし、むしろ役目を与えられて、生きる居場所が出来て、嬉しかったのである。
僕は彼女が欲しいというよりも、女の子に存在を認められたかった。存在が成立する為には、女の子に僕という存在を一人の人格としてを認識してもらい、そしてそれが僕にわかるかたちで反応を返してもらうことだった。コミュニケーションが成立することが必要だったのだ。会話ややり取りが成立すれば、それが命令だろうが、弄びだろうが、踏みつけだろうが、痛めつけだろうが、僕という存在が相手の女の子の中で成立していることに変わりはなかったのである。
だから好意的なやり取りに越したことはないが、たとえ負のやり取りでも、それが無視や絶縁でなければ僕は構わなかったのだ。極端な話、女の子に怪我をさせられても、たとえ殺されても、相手が僕という人格を認識し、僕にわかるように反応を返してくれた、という証拠になるのならそれでもきっと嬉しかった。いや、本当は痛いのは嫌だけど。だが自己評価が低い状態のままだったら、僕が存在するにはこれしか方法がないのだと絶望しながら受け入れていたかも知れない。
恐らく理解出来ない人には意味がわからないだろう。そこまで女の子に認めて欲しいのなら自分で勇気を出してちゃんと相手を口説けよ、相手に想いを伝えろよ、と言うかもしれない。普通はそう考えるのだろう。上手く表現は出来ないが、小さい頃から失敗を避けながら脆弱に育ってしまい、打たれ弱いなかで生きている実感を得ようとすると、そういう歪んだ実存形式になってしまうのである。
□Mにとってのコスプレ撮影は「僕が望む永遠」
さて、「よくあるエピソード」の垂れ流しをここまで続けてきたが、最後に少しくらいは評論としての体裁を整えておこう。M属性を持つようになる流れとして、いくつか押さえておきたい要素がある。
まずは少年時代に恋愛に関して挑戦と失敗を繰り返してきたかそうでないかということ。失敗や挫折を避けるような育ち方をすると、幼児的全能感を捨てられないまま大人になってしまう。転び方を知らないと脆弱なプライドを持ってしまい。自分が傷付かないことが大事になってしまうのだ。
次にそれに気が付き、反動で自己評価が一気に落ちてしまうことである。大きな挫折だろうが、上手くすれば改めて自分の足で立つきっかけとなるだろう。だが気付くのが遅ければ遅いほど、その時間の長さに比例して痛みは大きくなる。挑戦や失敗をする元気すらなくなると、他者からの承認が欲しくなり、依存心が強くなってしまうのだ。
大抵の場合、依存心が強い大人など誰も助けてくれない。もちろん女性もそんな男など見向きもしない。だが、ごく稀にこのタイミングで評価してくれる女性が登場するのである。ちなみにこの状態ではキャッチセールスや怪しい宗教からもカモにされるので要注意。
一度出会ってしまえば、後はもう承認してくれる女性の言いなりになる。M属性の完成だ。
ここで注目しておきたいのは、依存心の強い男と、手を差し伸べてくれる女性とが簡単に出会ってしまう空間がこの世に存在するということである。もうお分かりだろう。我らがコスプレイベントや撮影会の界隈だ。カメラを持っていればそのうちそれなりの写真が撮れるようになってくる。そこには魔の手が待ち構えているのである。僕と契約してマゾになってよ!
上記までのような過程でM属性を持つカメラ小僧は決して少なくない。冒頭で述べた三割という数字はきちんと統計的な調査に基づいたものではないが、カメラマンも女の子も多くは「大半がそうだという訳ではないが、このタイプは決してマイノリティーではない」という認識を持っている。そしてこのタイプのカメラ小僧はコミュニケーションスキルも低く勘違いもしやすいのである。
面倒なのはそういうM属性のカメラ小僧が「女の子に認めて欲しい」という承認に強く飢えているということだ。そして一度承認を与えられるとその女の子に好意を寄せて粘着してしまうのである。お互いの求めているものが一致すると仲の良い関係にもなれるだろうが、一歩間違えると非常に歪なギブアンドテイクの関係となるだろう。トラブルも本人たちだけで収束すればそれは二人だけの問題となるが、大抵は周囲に火の粉が掛かりとばっちりを受ける人が出てくる。もし周囲で見かけたら近付かないのが賢明だろう。君子危うきに近寄らず。
またM属性のカメラ小僧がずっとM属性を持ったままなのかといえば、必ずしもそうではないだろう。おちゃらけでそういうキャラを演じることはあるかもしれないが、さすがに歳を重ね社会に揉まれる中で自分でアイデンティティを確立し、Mを卒業していく人がほとんどだと思われる。
だが、一方でそこで失敗した人がこの「カメラ小僧界隈」で留年し続けていると言えるかも知れない。逆に言えば、カメラを持ってコスプレを撮っていれば、撮影という建前でコミュニケーションすることが出来、可愛い女の子から一定の承認を「与えてもらう」ことが出来る。そしてこの場で留年し続けようという意思があれば、永遠に居続けることが出来てしまう。ここはそういう場所なのだ。構造的にコミュニケーションスキルの無い人の為のセーフティーネットであり、どうしようもない人の溜まり場でもある。この点は問題提起としては重過ぎるので棚に上げてしまおう。後は知らん。
また逆に女の子にもM属性を持つ人はいる。コスプレや撮影関係の界隈にもそこそこ存在しているはずだ。決してSMプレイのMの役割が好みという話ではなく、ここでは存在を認めて欲しいタイプのことである。上記のエピソードの「僕」がそうだったように「与えてくれること」を常に求め続けるので、与える側になるのはそれなりに大変だろうとは想像するが、少なくともM男よりは需要がありそうなので「ご利用は計画的に」とだけ書いておく(汗。今回のテーマからもズレるのでM属性を持つ女の子の話は、もしご要望があれば『カメラ小僧の裏話6』で改めて筆を執ることとしよう(ぇ。
まずは少年時代に恋愛に関して挑戦と失敗を繰り返してきたかそうでないかということ。失敗や挫折を避けるような育ち方をすると、幼児的全能感を捨てられないまま大人になってしまう。転び方を知らないと脆弱なプライドを持ってしまい。自分が傷付かないことが大事になってしまうのだ。
次にそれに気が付き、反動で自己評価が一気に落ちてしまうことである。大きな挫折だろうが、上手くすれば改めて自分の足で立つきっかけとなるだろう。だが気付くのが遅ければ遅いほど、その時間の長さに比例して痛みは大きくなる。挑戦や失敗をする元気すらなくなると、他者からの承認が欲しくなり、依存心が強くなってしまうのだ。
大抵の場合、依存心が強い大人など誰も助けてくれない。もちろん女性もそんな男など見向きもしない。だが、ごく稀にこのタイミングで評価してくれる女性が登場するのである。ちなみにこの状態ではキャッチセールスや怪しい宗教からもカモにされるので要注意。
一度出会ってしまえば、後はもう承認してくれる女性の言いなりになる。M属性の完成だ。
ここで注目しておきたいのは、依存心の強い男と、手を差し伸べてくれる女性とが簡単に出会ってしまう空間がこの世に存在するということである。もうお分かりだろう。我らがコスプレイベントや撮影会の界隈だ。カメラを持っていればそのうちそれなりの写真が撮れるようになってくる。そこには魔の手が待ち構えているのである。僕と契約してマゾになってよ!
上記までのような過程でM属性を持つカメラ小僧は決して少なくない。冒頭で述べた三割という数字はきちんと統計的な調査に基づいたものではないが、カメラマンも女の子も多くは「大半がそうだという訳ではないが、このタイプは決してマイノリティーではない」という認識を持っている。そしてこのタイプのカメラ小僧はコミュニケーションスキルも低く勘違いもしやすいのである。
面倒なのはそういうM属性のカメラ小僧が「女の子に認めて欲しい」という承認に強く飢えているということだ。そして一度承認を与えられるとその女の子に好意を寄せて粘着してしまうのである。お互いの求めているものが一致すると仲の良い関係にもなれるだろうが、一歩間違えると非常に歪なギブアンドテイクの関係となるだろう。トラブルも本人たちだけで収束すればそれは二人だけの問題となるが、大抵は周囲に火の粉が掛かりとばっちりを受ける人が出てくる。もし周囲で見かけたら近付かないのが賢明だろう。君子危うきに近寄らず。
またM属性のカメラ小僧がずっとM属性を持ったままなのかといえば、必ずしもそうではないだろう。おちゃらけでそういうキャラを演じることはあるかもしれないが、さすがに歳を重ね社会に揉まれる中で自分でアイデンティティを確立し、Mを卒業していく人がほとんどだと思われる。
だが、一方でそこで失敗した人がこの「カメラ小僧界隈」で留年し続けていると言えるかも知れない。逆に言えば、カメラを持ってコスプレを撮っていれば、撮影という建前でコミュニケーションすることが出来、可愛い女の子から一定の承認を「与えてもらう」ことが出来る。そしてこの場で留年し続けようという意思があれば、永遠に居続けることが出来てしまう。ここはそういう場所なのだ。構造的にコミュニケーションスキルの無い人の為のセーフティーネットであり、どうしようもない人の溜まり場でもある。この点は問題提起としては重過ぎるので棚に上げてしまおう。後は知らん。
また逆に女の子にもM属性を持つ人はいる。コスプレや撮影関係の界隈にもそこそこ存在しているはずだ。決してSMプレイのMの役割が好みという話ではなく、ここでは存在を認めて欲しいタイプのことである。上記のエピソードの「僕」がそうだったように「与えてくれること」を常に求め続けるので、与える側になるのはそれなりに大変だろうとは想像するが、少なくともM男よりは需要がありそうなので「ご利用は計画的に」とだけ書いておく(汗。今回のテーマからもズレるのでM属性を持つ女の子の話は、もしご要望があれば『カメラ小僧の裏話6』で改めて筆を執ることとしよう(ぇ。
■おわりに
いかがでしたでしょうか。筆者としてはこれまでの中で一番痛々しさに満ちた本に仕上がったのではないかと自負しています。改めて読み返してみると、エピソードとして書いた部分は物語なのか随筆なのか、極めて不思議な文章になっていました(汗。なんだこれ。編集からは森鷗外の『舞姫』を彷彿とさせると言われましたが、筆者としては別にそれを意識した訳ではなく、書いていったらそうなっていました。個人的には谷崎潤一郎の『痴人の愛』のような、もっと倒錯的な描写にしたかったのですが「よくあるエピソード」ではなくなるので止めておきました。
執筆中特に印象的だったのは、Chapter.3の書き出しで数日間悩んでいたときに、iTunesからUNDER17の『1+1』が流れてきたことでした。桃井はるこの声で「君に大声を出してしまった──」から始まるフレーズは、いつも電波系ソングを歌っている彼女にしては妙にシリアスで、後悔に充ちていて、ここで書かなければならないイメージを一気に明確にしてくれました。
思えば拙い青春の記憶から創作をでっち上げる為に、執筆中ずっと音楽を聴いていました。高校の部分でTo Heartやカードキャプターさくら、大学の部分はglobeや倉木麻衣やオナニーマシーン、Chapter.2では桃井はるこ、Chapter.3では山崎まさよしの『One more time, One more chance』、ええ、よく死ななかったなと思います。「やめてくれやめてくれ」を連呼しながら書いてました(汗。
今回このテーマにしたのは、いつもイラストを描いて頂いてる高崎かりんさんがマンガを描いているときに「Mの心理描写をどうすればよいか悩む」とのことだったので、では解説を書いてみようというのがきっかけでした。
表紙のイラストもそれに合わせて岡田和人の『すんドめ』にするため、原作をかりんさんに読んでもらったのですが、やはりMの気持ちがピンと来なくて描くのが難しかったそうです。うーん、やはり女性には男性のMの心理がわかりにくいのかもしれません。筆者は『すんドめ』を涙なしには読めなかったのになぁ。そういう意味では今回の本は男女で感想が分かれるかもしれません。
さて、同人活動も3周年を迎えました。もうサークル参加が6回目だというのが未だに信じられません。大分ワークフローが完成して負担が減ったとはいえ、今回もいつも通り締切間際まで修羅場が続き、精神を削っているのは相変わらず。余裕が出来たら、その余裕の分だけギリギリまで執筆しているという(汗。明日印刷入稿なのに、睡眠不足で今この文章を書いています。横には溜まった仕事の山。書きたいテーマはまだまだたくさんあるのですが、この連日徹夜のマゾい活動はいつまで続けられるんでしょうかね。来年はもっと寝たいです。
最後に謝辞を述べさせて頂きます。高崎かりんさん、いつも素敵なイラストをありがとうございます。実は彼女とは前回の無茶発注のお詫びとして、女装&緊縛&百合&コスプレ合わせの撮影をしてきました。今回はちゃんと余裕を持って依頼しましたよ(キリッ!宜しければまたコスプレ合わせしましょう。当日の売り子予定の庶務部長さん、また休みを確保してくれてありがとう。カメラ小僧の評論本なのに、前回は「まどマギ本です!ほむほむ好きは買っていけ!」と半ば詐欺紛いの売り込みトークで凄まじく売れていきました(汗。今回も何を言い出すのか楽しみにしています。誌面デザインでお世話になっているののさん、いつもありがとうございます。今回からは大分負担が軽減された…はず(汗。来年からは更にこちらでの分担を増やしていきたいと思います。よろしくお願い致します。そういえば最近、霧雨魔理沙の抱き枕を買いました。あとiMacの傍らに宮川武制作の霧雨魔理沙フィギュアを飾って眺めながら執筆してました。同人活動を鼓舞してくれた彼女にもお礼を言わなければならないでしょう。ありがとう(終。
最後に、会場内で本書を手に取って下さった全ての方々に謝意を表し、今回はここで筆を置かせて頂きます。次回また濃くも痛々しい誌面上でお会いしましょう。皆様よいお年を。
2011年12月某日 職場のiMacにて
(↑結局MacBook Proはまだ買えてない)
よろず評論サークル「みちみち」代表 みちろう
執筆中特に印象的だったのは、Chapter.3の書き出しで数日間悩んでいたときに、iTunesからUNDER17の『1+1』が流れてきたことでした。桃井はるこの声で「君に大声を出してしまった──」から始まるフレーズは、いつも電波系ソングを歌っている彼女にしては妙にシリアスで、後悔に充ちていて、ここで書かなければならないイメージを一気に明確にしてくれました。
思えば拙い青春の記憶から創作をでっち上げる為に、執筆中ずっと音楽を聴いていました。高校の部分でTo Heartやカードキャプターさくら、大学の部分はglobeや倉木麻衣やオナニーマシーン、Chapter.2では桃井はるこ、Chapter.3では山崎まさよしの『One more time, One more chance』、ええ、よく死ななかったなと思います。「やめてくれやめてくれ」を連呼しながら書いてました(汗。
今回このテーマにしたのは、いつもイラストを描いて頂いてる高崎かりんさんがマンガを描いているときに「Mの心理描写をどうすればよいか悩む」とのことだったので、では解説を書いてみようというのがきっかけでした。
表紙のイラストもそれに合わせて岡田和人の『すんドめ』にするため、原作をかりんさんに読んでもらったのですが、やはりMの気持ちがピンと来なくて描くのが難しかったそうです。うーん、やはり女性には男性のMの心理がわかりにくいのかもしれません。筆者は『すんドめ』を涙なしには読めなかったのになぁ。そういう意味では今回の本は男女で感想が分かれるかもしれません。
さて、同人活動も3周年を迎えました。もうサークル参加が6回目だというのが未だに信じられません。大分ワークフローが完成して負担が減ったとはいえ、今回もいつも通り締切間際まで修羅場が続き、精神を削っているのは相変わらず。余裕が出来たら、その余裕の分だけギリギリまで執筆しているという(汗。明日印刷入稿なのに、睡眠不足で今この文章を書いています。横には溜まった仕事の山。書きたいテーマはまだまだたくさんあるのですが、この連日徹夜のマゾい活動はいつまで続けられるんでしょうかね。来年はもっと寝たいです。
最後に謝辞を述べさせて頂きます。高崎かりんさん、いつも素敵なイラストをありがとうございます。実は彼女とは前回の無茶発注のお詫びとして、女装&緊縛&百合&コスプレ合わせの撮影をしてきました。今回はちゃんと余裕を持って依頼しましたよ(キリッ!宜しければまたコスプレ合わせしましょう。当日の売り子予定の庶務部長さん、また休みを確保してくれてありがとう。カメラ小僧の評論本なのに、前回は「まどマギ本です!ほむほむ好きは買っていけ!」と半ば詐欺紛いの売り込みトークで凄まじく売れていきました(汗。今回も何を言い出すのか楽しみにしています。誌面デザインでお世話になっているののさん、いつもありがとうございます。今回からは大分負担が軽減された…はず(汗。来年からは更にこちらでの分担を増やしていきたいと思います。よろしくお願い致します。そういえば最近、霧雨魔理沙の抱き枕を買いました。あとiMacの傍らに宮川武制作の霧雨魔理沙フィギュアを飾って眺めながら執筆してました。同人活動を鼓舞してくれた彼女にもお礼を言わなければならないでしょう。ありがとう(終。
最後に、会場内で本書を手に取って下さった全ての方々に謝意を表し、今回はここで筆を置かせて頂きます。次回また濃くも痛々しい誌面上でお会いしましょう。皆様よいお年を。
2011年12月某日 職場のiMacにて
(↑結局MacBook Proはまだ買えてない)
よろず評論サークル「みちみち」代表 みちろう
■奥付
【誌名】カメラ小僧の裏話5 僕がMになったワケ
【発行年月日】2011年12月31日 コミックマーケット81 初版
2013年8月11日 コミックマーケット84 第二版
【構成・執筆】みちろう
【イラスト】高崎かりん
【編集】のの
【誌面デザイン】のの
【印刷】大陽出版株式会社
【発行サークル】みちみち
【発行責任者】みちろう
【ウェブサイト】http://miti2.jp
【連絡先】circle@miti2.jp
※本書内容の無断転載は固くお断りします。
【発行年月日】2011年12月31日 コミックマーケット81 初版
2013年8月11日 コミックマーケット84 第二版
【構成・執筆】みちろう
【イラスト】高崎かりん
【編集】のの
【誌面デザイン】のの
【印刷】大陽出版株式会社
【発行サークル】みちみち
【発行責任者】みちろう
【ウェブサイト】http://miti2.jp
【連絡先】circle@miti2.jp
※本書内容の無断転載は固くお断りします。
Copyright(C)2008-2025 miti2.jp. All Rights Reserved.